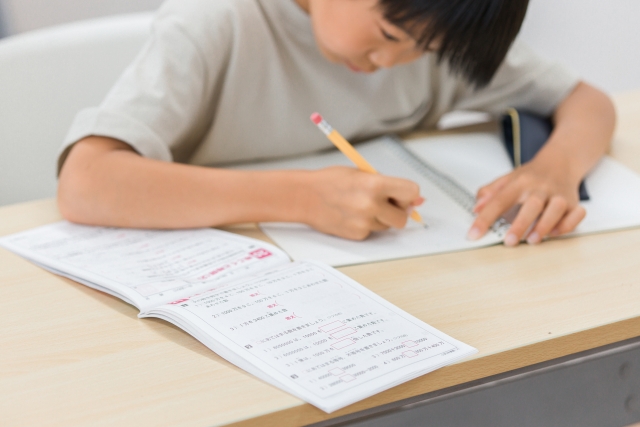中高一貫校教師歴30年で、我が子の中学受験も経験したベテランライターが、公立中学と私立中学の授業の違いを解説します。
学習指導要領に沿って「基礎学力」に主眼を置いている公立中学と、学校の独自性のもと「大学受験に最適化」しているケースが多い私立中学とでは、授業の中身は大きく違います。
多くの場合、私立中(中高一貫校)のほうが「授業時間が多い」「授業の進みが速い」「発展的な内容まで扱う」といった形で、学力を鍛えられます。一方で、対応するためには強度の高い自宅学習が不可欠で、負担は大きくなります。
お子さんの成長タイプが晩成型で、後伸びを期待したい場合や、10代前半を部活や課外活動などで自由度高く使いたい場合には、公立中学 → 高校受験ルート。
早期から競争が可能な学力があり、入学後も大学受験までを見据えてハイレベルな環境で鍛えたい場合には、私立中学(中高一貫校)ルートが選択肢になりやすいでしょう。
このページの目次
公立中と私立中の教育方針・学習目的・生徒層を比較
公立中:基礎学力重視で高校受験を目指した授業展開
公立中は、文部科学省の学習指導要領に基づき、全国共通のカリキュラムで運営されます。
全国共通の基準に沿っており、学校ごとの大きな差はなく、「基礎学力の定着」と「高校受験に向けた学び」が中心です。
- 教育方針:基礎から丁寧に「学ぶ力」「考える力」「生きる力」を育む
- 学習目的:各都道府県の入試に向けて定期テストや内申重視
- 生徒層:地元の中学生で学力差や意欲の幅が広い
公立中は「多様な人と関わりながら、社会で生きる力の基礎を育てる場所」として、学力面のみならず、部活動や地域活動を通して、人間的な成長が期待できる環境です。
私立中:学校の独自性のもと大学受験を見据えた授業展開
私立中は、それぞれの学校の建学の精神に基づいた独自のカリキュラムで運営されます。
学習指導要領をベースにしながらも、学校独自の進度・教材・取り組みなどが特徴です。
- 教育方針:先取り学習で中3から高校内容を学ぶ学校が多い
- 学習目的:大学進学を見据えたハイレベルの教育
- 生徒層:入試を突破した生徒が集まるので学力差が少ない
私立中のほとんどは中高一貫校で、進学が強みの進学校タイプや系列大学への進級を目指す大学附属タイプなどが主流です。いずれも「6年間の一貫カリキュラム」が組まれています。
6年間の豊富な時間を活かして、探究学習・課題研究・国際理解教育・ICT教育など学校ごとの特色があります。
詳しく知る:
授業時間数
公立中:年間1015時間を基準にゆとりあるスケジュール
公立中の年間授業時間数は「中学校標準授業時数」(学校教育法施行規則)によって、1015時間と定められています。地域や学校によって多少の差はありますが、全国的にほぼ統一されています。
授業時間の特徴は次の通りです。
- 通常は1日6時間授業
- 土曜授業は任意(年数回の行事や保護者向けの学校公開日など)
- 放課後や土日は部活・習い事・自主学習など自由に使える
公立中では、余白が多く、自分の裁量で使える時間が多いのが特徴です。
部活や習い事など、「得意」や「好き」を伸ばす時間を確保しやすく、子供の適性や家庭の方針に合わせた時間の使い方ができます。
私立中:7時間授業・土曜授業・長期休暇講習などを含めて豊富な授業時間
私立中は、学校の裁量でカリキュラムを設計できるので、年間で1200〜1400時間前後の授業時間があります。公立中よりも、1日あたり約1時間多く学んでいる計算になります。
それぞれの学校の授業時間はシリタスで調べることができます。
授業時間の特徴は次の通りです。
- 1日7時間授業の学校もあり
- 毎週(あるいは隔週)土曜日に授業
- 長期休暇中には講習・特別講座・補習あり
- 成績不振者には補習、上位者にはハイレベル講座など
- 休校時にはオンライン授業
授業時間が多いので、先取り学習や発展的な学習が可能です。難関大の合格実績では私立中高一貫校が上位を占めています。
教科書・副教材
公立中:検定教科書を使って基礎を丁寧に積み上げる
公立中では検定教科書と準拠ワークを使用します。検定教科書は、「義務教育として全ての生徒が無理なく学べる」ことを目的として編集されています。
代表的な検定教科書
- 英語:「NEW HORIZON」(東京書籍)「NEW CROWN」(三省堂)
- 数学:「新しい数学」(東京書籍)「これからの数学」(数研出版)「未来へひろがる数学」(啓林館)
代表的な副教材
- 教科書準拠ワーク
- 定期テスト向けプリント
- 高校入試用標準問題集
映像授業、通信添削、地元塾など、検定教科書に準拠した教育サービスが豊富に揃っています。
扱う内容は、基礎〜標準レベルが中心で、無理なく基礎を固めながら学力を積み上げられます。
学ぶべき範囲は、高校入試に直結していて、明確で的が絞れているため、迷走しにくいのも安心材料です。
私立中:検定外教科書・ハイレベル副教材を使った先取りと深掘り
私立中では、多くの学校で、検定外教科書(=中高一貫校用教科書)、ハイレベル問題集、学校独自プリントなどを使用します。
【英語】
代表的な検定外教科書(=中高一貫校用教科書)
- 「NEW TREASURE」(Z-KAI)
- 「PROGRESS IN ENGLISH」(エデック)
代表的なハイレベル問題集
- 「新中学問題集 発展編」(教育開発出版)
- 「Sirius 21 発展編」(育伸社)
- 「徹底反復シリーズ 5 STAGE 英文法完成」(数研出版社)
上記のテキストなどを使って、次のいずれかの組み合わせで授業展開しています。
- 検定外教科書+準拠問題集(もしくはハイレベル問題集)
- 検定教科書+ハイレベル問題集
いずれの組み合わせにしても、スタート段階では、初学(公立小学校で学習したレベル)で対応可能ですが、進度が速く、中3からは高校レベルの単語・文法・読解を学習に移行します。
詳しく知る:
【数学】
代表的な検定外教科書(=中高一貫校用教科書)
代表的なハイレベル問題集
- 「STEP演習 中学数学」(数研出版)
- 「新中学問題集 発展編」(教育開発出版)
上記のテキストなどを使って、次のいずれかの組み合わせで授業展開しています。
- 検定外教科書+準拠問題集
- 検定教科書+ハイレベル問題集
検定外教科書では、本来は「等式」=中1、「不等式」=高1で習うのを、「等式」と「不等式」を連続して習います。つながりを意識した構成で、中学から高校内容を学習します。
検定教科書を使うケースでは、中2までに中学内容を全て終わらせて、中3から高校内容がスタートするのが標準的です。
詳しく知る:
【国語・理科・社会】
検定教科書を使って授業を展開する学校が多いのですが、補助教材や学校独自のプリントを使って高校内容まで深掘りします。
例えば、中学で物理の分野を学べば、高校内容まで教えることもあります。
「先取り」よりも「探究」「考察力」を重視して、「考える力」を伸ばす授業を展開しています。
授業の難易度・速度
公立中:「基礎力重視」でゆるやかな学習進度と「学びのプロセス」を重視
基礎重視
公立中では、学習指導要領に基づき、全員が理解できるように丁寧に進めます。応用よりも基礎の定着を重視して、勉強が苦手な生徒を置き去りにしない設計になっています。
基礎をしっかり固めていくので、勉強で落ちこぼれるケースが少ない点は安心材料です。
その上で、実は、授業内容も親世代から比べると十分に進化しているのです。
例えば、英語では、小学校での英語必修化を受けて、学習レベルが上がっています。単語数は1200語から1600語〜1800語に増えて、これまで高校で習っていた仮定法や原形不定詞などが中学で習うようになりました。
内申重視
テストの点数だけでなく、授業態度や提出物などの日常の取り組みが重視されます。
観点別評価の導入によって、以下のように多角的に学力が評価されます。
- 「知識・技能」
- 「思考・表現・判断」
- 「主体的な態度」
これらは相対評価ではなく、絶対評価で評価されます。そのため、努力が評価に反映されやすい仕組みになっています。
内申点が入試結果に影響を与えることを鑑みると、学力試験の一発勝負にならない点にも注目すべきです。
「授業→定期テスト→内申点→高校入試」とするべきことがはっきりしていて、努力が成果に結びつきやすいのもメリットです。
プレゼンテーションやアクティブラーニング型の授業展開も充実し、それぞれの意見を発表する機会が豊富です。また、「振り返りシート」を使って学びのプロセスが重視されているのも特徴です。
私立中:中2までに中学内容を終わらせて中3から高校内容へ
先取りと深掘り
私立中(=中高一貫校)では、大学受験を前提にした6年間一貫のカリキュラムが組まれています。中学3年間を高校受験対策に使う公立中とは、そもそもの設計が違います。
多くの学校が採用しているのは、次のような先取りカリキュラムです。
- 中1〜2:中学範囲
- 中3〜高2:高校範囲
- 高3:入試演習
更に、大学入試を見据えた深掘り学習も特徴です。
例えば、中学の物理分野で高校物理を扱ったり、中学の英語で高校レベルの長文読解に取り組むなど、発展まで踏み込んだ学習をします。
詳しく知る:
難易度が高く、家庭学習が必須
私立中は入試を経て入学しており、生徒の学力差が小さいのが特徴です。
「入試に合格=学校の授業レベルに対応できる学力」という前提で授業が展開し、授業スピード・テキストレベル・定期テスト難易度が相応に設定されています。
そもそもかなりの学習量が求められます。「能力差」よりも「学習量」で差がつく傾向があり、家庭学習がままならないと思いがけない成績低迷のリスクがあります。
学校独自のカリキュラム・授業内容
公立中:地域や自分の将来に密着した学び
地域社会とのつながりを大切にして、生徒一人ひとりが将来を設計できる教育をします。自治体や学校ごとに特色のある活動があります。
地域に根ざした教育
行政や地域企業と連携した職業体験、ボランティア活動や地域行事などを通して、「社会とのつながり」を学び、それぞれの将来について考えるきっかけを与えます。
外国語教育
英語では、ALT(外国語指導助手)と日本人教師によるTT(チームティーチング)が行われています
小学校からの英語教育の流れを継続しながら、ALTとの会話練習、プレゼンやスピーチ活動など実践的な英語学習を取り入れています。
ICT教育
文部科学省の「GIGAスクール構想」により、一人一台のタブレット端末が整備されています。ICT教育を推進して、タブレットを使った調べ学習やプレゼンテーションなども積極的に取り入れています。
教育委員会が主導して、多様な実践例が各学校で共有されているのも強みです。
私立中:学校の強みを活かして多様な選択肢
大学受験を見据えた進学教育だけでなく、探究学習・ICT教育・国際理解教育など、多彩な学び方があります。
探究学習
大学での学びや職業選択を見据えて、探究学習が重視されています。「自分で問いを立てて、考えて発信する力」を育みます。早い段階から進路を意識した教育が行われます。
- 全員向けの「全員参加型探究学習」と希望者向けの「Project Based Learning」
- 中3で「10年後の自分が社会とどう関わるか?」をテーマに研究・発表
国際理解教育
英語教育に力を入れている学校が多いです。ネイティブ講師の英語授業・海外研修・海外修学旅行・英検講座(準2級・2級の取得支援)などが特徴です。
- 最大9カ国を訪問する海外研修プログラム
- ネイティブ専任講師による英語コミュニケーションの育成
- オーストラリア修学旅行
ICT教育
ICT環境が整備されておりタブレット端末を使用した学習が一般的です。
- 生徒全員がタブレットPCを所有
- 学習支援アプリ(Classi・ロイロノート)を使って資料や解答の共有(双方向授業)
- 英語4技能e-ラーニングシステムの活用
公立中と私立中を選ぶ判断基準
公立中の「基礎固めと自由度」か?私立中の「先取りと受験最適化」か?
公立中は「ゆっくり丁寧に」「自由に幅広く」のスタイルで、私立中は「ハイレベルで先取り」「大学受験に最適化」のスタイルと言えます。
どちらも一長一短があり、どちらが合うかは子供の適性や家庭の方針次第です。
公立中の学習スタイル
公立中の授業は基礎重視で、大学受験を見据えると物足りないと感じるかも知れませんが、決してそうとは限りません。
発展的な内容を学びたい場合は、目的に合わせたピンポイント補充をしましょう。
映像授業・通信添削・地元塾など、公立中のカリキュラムに準拠した教育リソースが充実しているので、本人の適性や家庭の方針に合わせた補強の選択肢が豊富です。
例えば、英語塾を使って英語だけ先取りすることも可能です。英語が得意だと、高校受験だけでなく、大学受験でもアドバンテージです。
その意味では、タイパ(時間効率)やコスパ(費用対効果)よく、自分の強みを伸ばすことができます。
また、各自の裁量で勉強を進めることができるので、自主性や自学力を育み、「後伸び」する要因にもなります。
私立中の学習スタイル
私立中では、大学受験に最適化した授業が展開されており、授業にきちんとついていけば確かな実力を身につけることができます。
大学進学(特に難関大や理系)などを見据えると、方向性に無駄がありません。
その反面、進度が速く内容も高度なため、授業についていけなくなるリスクも否定できません。
授業で学んだことは、家庭学習でしっかりと復習と演習をして定着させるのが前提となっています。家庭学習が不足すると、授業についていけなくなる可能性があります。
成績不振者には、補習や個別指導などのサポート体制を整えていますが、授業自体の進度を遅らせることはありません。そのため、家庭学習の積み重ねが非常に大事です。
学力がつかないまま中学を終えると、高校に進級できないケースや、進級しても授業についていけずに苦労するケースが生じます。
詳しく知る:
「高校受験」を目指すか?「中学受験」を目指すか?
公立中と私立中の授業の違いを理解すると、どちらの環境が子供に向いているかがわかります。
結局のところ、「中学受験と高校受験のどちらを目指すか?」が重要な視点です。
高校受験を目指す:公立中→高校受験ルート
公立中を選ぶ場合は、小学生の間は伸び伸びと過ごせます。習い事や自分の得意や好きを伸ばすなど、様々な体験に時間を使える点が大きなメリットです。
中学受験がないからこそ、親のサポートによる影響が大きくなります。基礎学力の定着、学習習慣づくり、さまざまな体験の機会などは、親の働きかけに左右されます。
精神年齢が幼い「後伸びタイプ」の子にとっては、中学受験を回避して、公立中から高校受験で力を発揮するのも有力な選択肢です。
子供が自分の意思で将来の方向性を定めやすいというメリットもあります。
公立高校の大学進学状況
公立高校には、難関校から中堅校、実業系まで選択肢が豊富です。
都立の難関校であれば、東大をはじめとする難関大を目指すのは十分可能です。中堅校からでも、GMARCHや日東駒専の進学実績も多く、大学進学のチャンスは十分に確保されています。
中学受験で、GMARCHや日東駒専の付属中学に合格するのは難易度が高く、公立中→公立高からでも、十分に同レベルの大学進学を目指せます。
総合型選抜や学校推薦型選抜を使った進学も増えています。実業系高校からでも、簿記などの資格取得を活かして大学進学するルートがあります。
私立高校も有力な選択肢
近年では授業料無償化の流れもあり、私立高校の人気も高まっています。特に早慶付属校は中学受験よりも高校受験の方が入りやすいという定説もあります。
その理由として、「科目数が少ない」「中学受験で上位層が抜ける」「定員よりも合格者数が多い」などが挙げられますが、いずれにしても難易度が高いので注意が必要です。
私立高校には複数のコース(特別進学・特進・進学など)があり、コースごとに偏差値が異なります。
併願優遇制度が広く利用されています。これは、第一志望で都立高校が不合格の場合は、内申点の基準を満たしていれば事実上合格が保障される制度です。一方で、併願優遇を使わないフリー受験は難化傾向です。
高校受験に向いているタイプ
- 小学生時代に様々な体験を重視したい
- 自主性を尊重したい
- 後伸びタイプ
- 家庭で学習環境を整えられる(小学時代の英語・学習習慣など)
中学受験を目指す:中高一貫校ルート
私立中を目指す場合は、小学生の段階で中学受験を挑むことになります。そのため、親の意向や教育方針を反映させやすいという特徴があります。
高校受験がないので、中高6年間を計画的に大学受験にフルに活用できるのもメリットです。
事実、難関大の合格実績では中高一貫校が上位を占めています。
中学受験に向いているタイプ
- 勉強が得意で早い時期から意欲的に勉強できる
- 保護者が受験に積極的に関わりたい
- 難関大学を目指す最短ルートを取りたい
FAQ
-
Q 私立中と公立中では、授業時間や進度にどんな違いがありますか?
A多くの場合、私立中(中高一貫校)のほうが授業時間が多く、中高6年間の学習内容を5年間で学ぶ先取りを行い、発展的な内容まで扱います。学力が問われるタイプの大学入試では、明確に有利です。
公立中は標準授業時数に沿って1日6時間前後。土曜授業は自治体により異なるものの限定的で、基礎内容を全員が理解できるペースで進みます。「後伸び」タイプのお子さんにメリットがあります。 -
Q 公立中と私立中のどちらが子どもに向いているか、判断するポイントは何ですか?
A子どもの学力・性格と、家庭がどこまで受験や学習に時間と手間をかけられるか? で判断すると良いでしょう。
公立中は、地元の多様な生徒と一緒に基礎を丁寧に学びつつ、部活や習い事にも時間を使いたい子や、精神的な成長を待ちながら「後伸び」を期待したい家庭に向いています。
私立中は、まず中学受験を突破できる学力と学習意欲があるかどうかがポイントです。さらに私立中への入学後も、大学進学を早い段階から見据えてハイレベルな授業についていく覚悟がある場合に選びやすい進路です。 -
Q 公立中を選んでも、将来の大学進学の選択肢は狭くなりませんか?
A公立中からでも、公立・私立を含む多様な高校を選べて、難関校であれば東大をはじめとする難関大学への進学実績も十分あります。
中堅レベルの高校からでもGMARCHや日東駒専への進学例が多く、実業系高校から資格取得を活かして大学進学を目指すルートもあります。
さらに、一般選抜(テスト入試)だけでなく、総合型選抜や指定校推薦などの制度も増えており、公立中ルートでも、本人に合った高校選びと継続的な学習で多様な大学進学が可能です。