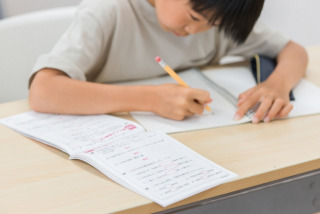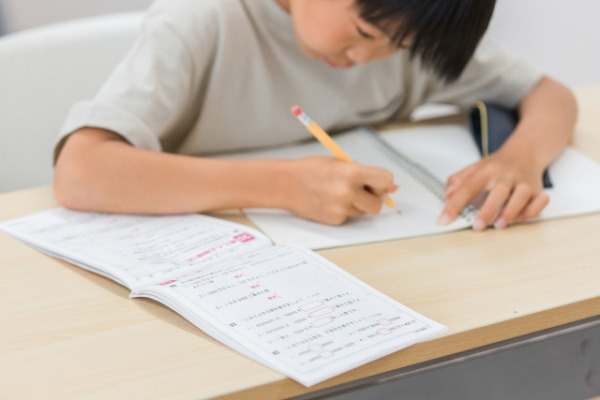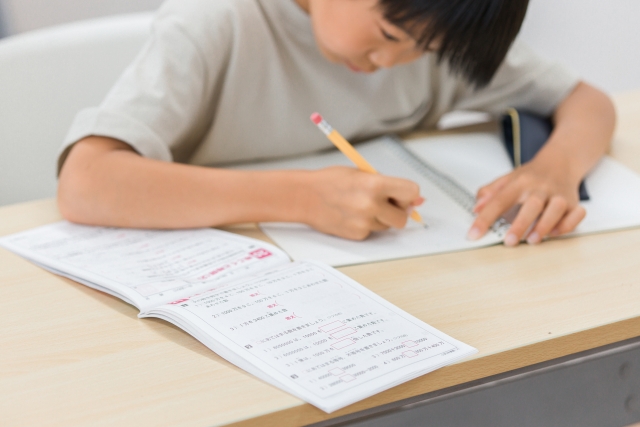中高一貫校教師歴30年で、自身の2人の子供も中学受験を経験したライターが、中学受験塾に通っても成績が上がらない原因とその解決策を紹介します。
成績が上がらない原因は、勉強の取り組み方が適切ではないためです。
- 間違った問題を放置せず、解き直す
- アウトプットを重視して勉強する
- 時間を区切って集中して勉強する
- 苦手科目から逃げず、しっかり対策をする
次のような勉強ができているか確認し、親が必要なサポートをしましょう。
このページの目次
勉強しているのに成績が上がらない原因:子どもの勉強の取り組み方【4選】
勉強しているのに成績が上がらない。親としては心配になりますが、まずやるべきことは、「原因を探ること」です。
子供の勉強の仕方について、次のチェックポイントに当てはまるものがあれば、それがまさに成績が上がらない原因です。
①勉強不足:「塾に通っているだけ」になっていませんか?
「塾で理解して、家庭で定着」のサイクルが回っていない
塾に通っていると、それだけで勉強したつもりになりがちですが、塾はあくまでも「理解」の場であり、家庭学習は欠かせません。
大切なのは、塾で「理解」して、家庭で「定着」させることです。
- 塾で習った内容の予習や復習
- 塾で出された宿題や課題
- 単元テストや模試に向けての勉強
などを家庭でしっかりこなして、自分のものにしないと成績は上がりません。
少し勉強したら成果が出ると思って、粘りが足りない
覚えた知識は、繰り返して定着させないと忘れてしまいます。その上で、知識を使えるようにするには、十分な演習が必要です。
「知識」を定着させて、知識が「使える」ようになって点数が上がる。このことを考えれば、勉強の成果が出るまでには、ある程度の時間が必要です。
すぐに結果を求めるのは間違いです。「少しずつ力がついている」と信じて、粘り強く勉強しないと成績は上がりません。
《我が家の長男の体験談紹介》 小6の1学期が終わる頃に、理科の範囲学習が終わりました。しかし、模試では、偏差値が50に届かないこともあり、特に物理分野を苦手としていました。 生物や地学のように、「覚えればある程度解ける」単元とは違い、物理は「考えて問題を解く力」が必要です。知識を覚えただけでは点数にはつながりませんでした。 最初の1〜2ヶ月は、スタディサプリの映像授業を使ったり、私が横について教えたりして、基本から学び直しました。この時期は努力の割には、得点が伸びずに、本当に辛かったです。 それでも諦めずに続けると、基本問題は解けるところまできました。そして、3ヶ月が経った頃に、標準問題が解けるようになり、ようやく模試の点数が上がり始めたのです。 全範囲をカバーできたわけではなかったので、点数は安定しませんでした。それでも、「確実に前に進んでいる」と感じることができたのが励みになりました。 これを境に、やる気も上がり、基本→標準→応用と着実に積み上げて、得点も安定してきました。 すぐに結果は現れませんでしたが、3ヶ月かけて基礎を固めた頃から、手応えを感じられるようになったのです。
②基礎力が不十分:「ミスによって得点が不安定」になっていませんか?
算数:計算力が不十分で、ミスによる失点が目立つ
算数で最も差がつくのは実は計算力です。
思考力や応用力はもちろん大切ですが、計算が正確でなければ、いくら解法が分かっても正解には辿り着けません。
算数では、計算問題が必ず含まれます。また、配点そのものが高い学校も少なくありません。
例えば、1問4点の計算問題を2問間違えると、それだけで8点落とすことになり、合否に直結します。
文章題や図形問題で解法がわかっていても、最後の計算で間違えれば「不正解」です。
また、1つの計算ミスが連鎖して、問題が解けないこともあります。
そもそも計算力があると、解くスピードが上がり、解答時間に余裕が生まれます。
このように計算力こそ、算数の「土台」そのものです。
国語:語彙力が不十分で、読解力がついていない
国語の問題では、漢字や語句問題で10点以上占めることもあります。
また、記述問題での漢字ミスは減点対象です。これだけをとっても漢字は大事だとわかります。
また、漢字を「意味」から覚えれば、自然と語彙力がつきます。
語彙力は読解力の向上に直結する重要ポイントです。
また、語彙力は他教科にも影響を及ぼします。
例えば、語彙力がつけば、「社会の用語や固有名詞を正確に理解できる」や「理科の現象を正確にイメージできる」などの利点があります。
基本問題が解けずに得点が安定しない
中学受験では基本問題が解けるだけで得点が安定します。また、ケアレスミスでの失点も減らすことができます。
そもそも、応用問題といえども、「基礎の組み合わせ」で作られています。
基礎を固めることこそ、成績を上げるためには大切です。
③勉強が非効率:「勉強しているつもり」になっていませんか?
解き直しをしないで、いつまでも解けない問題が解けないままになっている
テストの点数が伸びるのは、解けない問題が解けるようになったときです。
つまり、間違えた問題こそ点数アップのチャンスと言えます。
間違えた問題や苦手な問題を放置していたのでは、成績は上がりません。
まとめや暗記だけで、実際に問題を解いていない
「ノートをまとめる」「要点を覚える」などだけでは、実践力がつかないので、得点アップにはつながりません。
実際に「問題を解いて」みて、自分だけで問題が解けるようになるまでが勉強です。
自力で問題を解く勉強が足りないと、成績は上がりません。
勉強がただの作業になっている
子供部屋で勉強しているように見えても、「ノートを写しているだけ」「テキストを眺めているだけ」などになっていることがあります。
これでは、勉強というよりもただの作業に過ぎません。
机についているからと安心してはいけません。実際には、「ボーッとしている」だけで、学習内容が頭に入っていないことも多いです。
④精神面が不安定:「勉強に集中できていない」になっていませんか?
成績が上がらないのは、勉強の仕方に問題があるだけでなく、子供の精神面に問題があるケースもあります。
「やらされている感」で受験が「自分事」になっていない
「親に言われたから受験する」と受け身の姿勢では、勉強のモチベーションが上がらず、成績も伸びません。中学受験が「自分事」になっていないのが原因です。
「行きたい学校がない」「習い事や自分の好きなことを優先したい」など、理由は様々かもしれませんが、やらされている感を持っている限りは、成績は上がりません。
詳しく知る:
「不安」や「焦り」で勉強が手についていない
「どうせ自分には無理」「成績が悪いと怒られる」など、自分に自信が持てずに、精神面が不安定だと成績は伸びません。
どれだけ良い環境を与えても、子供の気持ちが前向きにならない限りは、本気で勉強に取り組めないものです。
勉強しているのに成績が上がらない原因:親の関わり方【2選】
成績が上がらないのは、お子さんの勉強の仕方に問題があるだけではありません。
実は、親の関わり方に問題があるケースもあります。
①子供の勉強に関わらない:「塾に任せておけば大丈夫」と思っていませんか?
子供の学習状況を把握していない
塾は非常に重要なのは間違いありませんが、塾に任せっぱなしで、子供の勉強のサポートが不足すると成績は伸びません。
- 学習内容(「何を習っているのか?」)
- 学習量(「どれくらい勉強しているか?」)
- 理解度(=「どれくらい理解しているか?」)
などを把握していないと、「苦手分野の対策が遅れる」のような状態になってしまいます。
また、受験当日だけでなく、模試やクラス編成テストなど、プレッシャーのかかることが多くあります。
子供の精神状態を把握していないと、勉強のスランプに陥ってしまうかもしれません。
子供の勉強の仕方を把握していない
塾の勉強だけでは成績アップは期待できません。
予習・復習・宿題・テスト勉強など家庭学習が伴って、初めて成績が伸びるのです。
もし子供が間違ったやり方で勉強していたら、例え努力をしていたとしても、時間を無駄にしてしまうことになります。
子供の勉強の仕方を見極めて、正しい方向へサポートをするのが大切です。
②子供の実力を把握していない:「これくらいやれば出来る」と思っていませんか?
高望みの志望校で子どもに過度に要求している
子供の学力を正しく把握していないと、「これくらいやれば出来る」と思い込んで、知らず知らずに過度な要求をしてしまいます。
子供の学力以上の志望校を押し付けて、過度なプレッシャーを与えかねません。
その結果、学習意欲が低下して、成績の伸び悩みを招きます。
他人と比べて親自身が焦っている
友達や兄弟、さらには自分の子ども時代と比べて、親自身が焦ってしまうことも少なくありません。
親の焦りは子どもに悪影響を与えます。焦りから、「あれこれと手をだす」「難しい問題に取り組む」など、サポートが迷走して、成績が伸び悩む原因になります。
否定的な声かけで子どもにプレッシャーを与えている
結局のところ、「子どもの実力を把握していない」「志望校と学力のギャップが大きい」「他人と比べて焦る」など、親自身の不安から、子どもにプレッシャーをかけてしまいがちです。
このようなケースでは、「なんでできないの?」のような否定的な声かけが増えてしまいます。
親子関係がギクシャクしてしまうと、子どもは安心して勉強に専念できません。
成績が上がらない場合に48時間以内に変える|勉強のやり方・学習環境・親の関わり方
成績が上がらない原因が分かれば、次は実際に取り組み方を変えてみましょう。
ここで紹介する5つの解決策は、すぐに実践できることばかりです。
ぜひ今日から、お子さんの受験勉強に取り入れてみてください。
【解決策①】間違った問題の解き直しを徹底する
間違った問題こそが伸び代!解き直しを徹底
「解けなかった問題が解けるようになる」のが成績が伸びている証です。
つまり、間違った問題が伸び代そのものなので、解き直しこそが最も大事です。
まずは、間違った問題の解説を丁寧に読んで、しっかり理解しましょう。
子供だけで理解できない場合は、親が教えたり、必要に応じて、家庭教師や個別指導を利用してください。
解答の丸暗記だけでは意味がありません。子供が一人で解答を再現できるように、「なぜそうなるのか?」を理解するのが大事です。
理解できたら、もう一度、子供だけで解き直します。
更に、数日後に解き直して、定着しているか確認しましょう。こうした繰り返しによって実力が定着していきます。
また、間違った原因の分析も忘れずに。
「知識不足だったか?」「解き方を知らなかったのか?」「単なるケアレスミスなのか?」と原因を把握して対策すれば、同じ間違いを防ぐことができます。
間違った問題をファイルにまとめておくと便利です。模試や入試前に解き直すことで得点アップが期待できます。
子供だけでは、解ける問題ばかり解きたがります。
そうならないためにも、親が関わって、解き直しを管理しましょう。
【具体例】模試の解き直し
【解決策②】インプット→アウトプットのサイクルで勉強する
インプットしたら必ずアウトプットを意識して勉強する
「解き方は覚えているのに解けない…。」成績が伸び悩んでいると、このようなことは頻繁にあるものです。
勉強は「覚える」よりも「使う」ことで定着するのです。
テストは「知っているか?」ではなくて、「解けるか?」が問われるので、実際に自分で問題を解く勉強を重視してください。
インプットとアウトプットは3:7が理想的と言われています。
インプット(「授業やテキストで解法を理解」「テキストやノートで知識を暗記」など)したものは必ずアウトプット(「例題・類題を解く」「解き直しをする」など)という流れを意識しましょう。
【具体例】塾のテキストを使ってインプット→アウトプット 【算数】 【社会】
【解決策③】時間を区切って集中して勉強する
30分1セットの単位で集中力を保って勉強する
子供が集中できる時間にも限界があります。
集中力が続かないなら、25分勉強→5分休憩のサイクルで勉強してみましょう。
2時間連続でダラダラ勉強するよりも、25分勉強→5分休憩を4セット回す方が、集中して勉強ができるはずです。
スキマ時間勉強をルーティン化する
スキマ時間を有効に活用すれば、勉強時間を伸ばせます。
例えば、
- 朝、小学校に通う前に5分間計算問題を解く
- 帰宅してから塾までの時間に映像授業を見る
- 塾に行く電車の中で社会の用語を暗記する
あらかじめすることを決めておいて、スキマ時間の勉強をルーティン化しましょう。
ルーティン化すれば、「何をしようかな?」と考えないで済むので、スムーズに勉強ができます。
学習環境を整えて集中力を保って勉強する
集中できる環境作りも非常に大事です。
- 机には物を置かないで広々と使う
- ゲームはマンガなど気の散るものは目のつかないところにしまう
など、集中しやすい環境を整えましょう。
子供が勉強している時はテレビを消すなど、家族で協力するといいですね。
【具体例】30分1セットの勉強サイクル
【解決策④】苦手科目から逃げないで勉強する
苦手科目こそ基礎から勉強する
苦手科目ほど、つい後回しにしがちですが、苦手科目から逃げていたのでは合格は遠のきます。
中学入試は4科目しかないので、どの科目も避けては通れません。
苦手科目こそ基礎の基礎から始めてみましょう。
算数なら計算、国語なら音読などです。
「是が非でも、点数を伸ばす」と力むことなく、まずは苦手科目の勉強に慣れるところからで大丈夫です。
少しずつ「わかる」「できる」が増えてくることで、達成感を感じてやる気が出るものです。
苦手科目こそ、教えるのが上手なプロ(家庭教師や個別指導)を活用するのも有効です。その科目の楽しさを伝えてくれることでしょう。
【具体例】苦手科目の勉強法 例)算数のつるかめ算
【解決策⑤】子どもの本当の実力を把握してサポートする
「点数」ではなく「内容」を見極める
模試の偏差値、順位、判定は現状を表しているにしか過ぎず、合否を保証するものではありません。
「数字」ではなく、「中身」を見るようにしてください。
例えば、「どの分野や単元が苦手か?」「前回と比べてどうか?」「同じミスを繰り返していないか?」などを精査しましょう。
子どもの学習状況を把握して、これからのサポートに活かすのがポイントです。
塾の先生と情報を共有する
親は受験のプロではありません。わからないことや不安なことがあれば、遠慮なく塾の先生に相談しましょう。
「算数が苦手みたいだけどどうすればいいか?」などアドバイスを求めれば、家庭でできることをお子さんの学力から判断して具体的に教えてくれるはずです。
「子どもがやる気が出なくて困っている」など、親の悩みや不安を聞いてもらうのも有効です。
塾の先生はこれまでに多くの受験生の親を見てきています。多くの親が同じように感じていると共感してくれるでしょう。
家での様子は塾での様子を積極的に情報交換しましょう。
現状を整理できれば親の安心につながります。安心して勉強できる環境を与えることが最高のサポートになります。
子どもの勉強に積極的に関わる
「塾に行っているから大丈夫…」「勉強は教えられないから…」「仕事が忙しいから…」などと、子供の勉強を塾に任せきりにしていませんか?
まだまだ小学生。中学受験では、成績を伸ばすためには、親の関わりは不可欠です。
子供にとって親は、「受験を支えるコーチ」です。どうすれば、子どもの点数が伸びるかを一緒に考える存在になりましょう。
例えば、「どうすれば次はできるようになる?」「今日は何なら集中できるかな?」などと問いかけてあげれば、子供の考える習慣を身につけて、自分で工夫するようになります。
そもそも中学受験は子供にとっては大きな挑戦です。
簡単に志望校合格を勝ち取れるようなものではありません。
だからこそ、結果よりも努力のプロセスに注目しましょう。「集中しているか?」「苦手科目を逃げていないか?」など、努力の過程が大切です。
たとえ志望校合格に届かなくても、受験を通して人間的に成長しています。
「叱責」よりも「前向きな声かけ」を心がければ、子供の学習意欲が高まるものです。
FAQ
-
Q 塾に通っていても成績が上がらないのはなぜですか?
A「塾で学習した内容を定着させるために必要な、家庭学習を行っていない」または「算数の計算力、国語の語彙力・読解力など、基礎が固まっていない」のが理由であることが多くなっています。お子さんの勉強に積極的に関わり、今どのような勉強をしているか、どこでつまづいているかなどを把握して、対処できるようにしましょう。 -
Q 成績を上げるために、明日から何を始めればいいですか?
Aお子さんの学習に積極的に関わり、状況を把握した上で、学習方法の見直しを行ってください。特に「間違えた問題は、解き直しを徹底する」「塾で習った内容を、家でもう一度取り組んで定着させる」の2点は不可欠です。 -
Q 親としてどう関われば、子どもの成績向上を支えられますか?
A第一に、お子さんの実力を正しく把握し、どのような課題があるか認識することが大切です。過度な志望校設定や、他の子との比較、焦り、否定的・批判的な声かけは禁物です。学習環境を整える(机まわり、スキマ時間、休憩サイクル)、集中できるルーティンづくりをする、といったサポートも有効です。