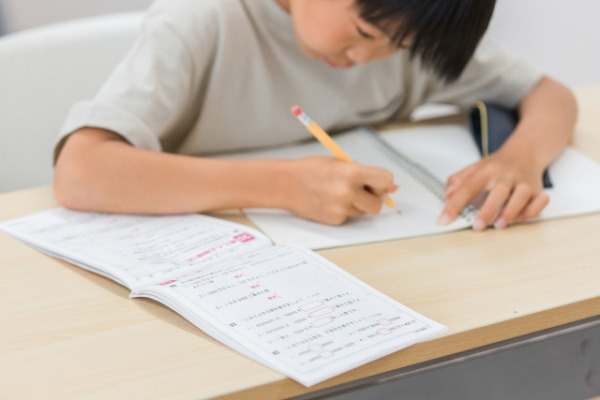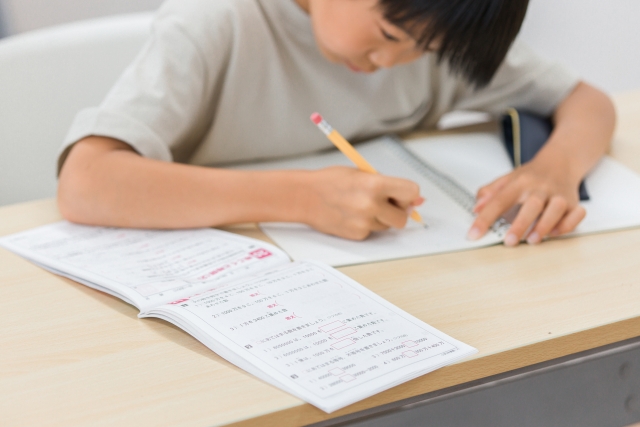
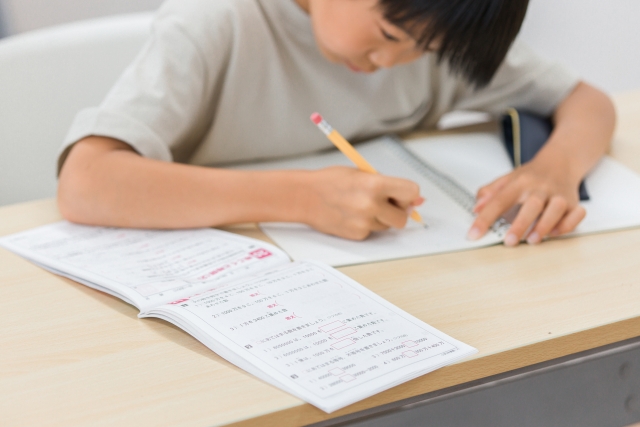
家庭の方針や、お子さんの状況によって、一概には言えませんので、次の5点を熟慮した上で判断しましょう。
- 子供の意欲
- 子供の様子
- 志望校のレベルと学力差
- 塾のスケジュール
- 習い事の将来性
なお、小学6年生の一年間は、習い事を中断し、受験に専念することを検討してください。
現役の中高一貫校教師であり、2人の子どもを中学受験で中高一貫校に送り出したライターが、中学受験と習い事を両立するメリット・デメリット、そして実際の両立方法を詳しく解説します。
このページの目次
習い事を辞めたくない!習い事を両立させるメリットとデメリット
受験勉強と習い事の両立は簡単ではありません。
でも、せっかく続けている習い事を諦めてしまうのも気が進まず、「習い事を辞めたくない」というケースも少なくありません。
まずは、中学受験と習い事の両立の「メリット」と「デメリット」を考えてみましょう。
習い事を続けるメリット
メリット①集中力や体力が身に付く
ピアノや習字のような毎日コツコツと取り組む習い事は、努力を積み重ねる習慣を自然と身につけることができます。この「継続する力」は、まさに受験勉強に直結する大切な要素です。
サッカーや水泳のようなスポーツ系の習い事は、体力を養うのに最適です。体力があると長時間の勉強にも耐えられ、受験本番の最後の追い込みで力を発揮できます。
さらに、スポーツでは「勝利から逆算して、日々の練習を組み立てる」という考え方を身につけることができます。これは逆算思考と呼ばれ、受験における「合格から逆算して学習計画を立てる力」と同じで、大きな武器になります。
将棋やそろばんのような習い事は、思考力や集中力を鍛える絶好の機会です。何事でも集中して取り組む習慣が、受験勉強の効率を高めてくれます。
このように、子どもが自分の好きなこと・得意なことを通じて、学力以外の素養を育むことができるのも習い事の大きな魅力です。
メリット②気分転換になる
中学受験をすると、どうしても勉強中心の生活になります。
小学生でありながら、勉強に追われる日々は、子どもには大きなストレスです。自分の好きな習い事に取り組む時間は、貴重な気分転換です。
特にスポーツのように体を動かす習い事は、シンプルに楽しく、心身ともにリフレッシュできる効果があります。
リフレッシュできる時間があると、結果的に学習効率が上がることが期待できます。
メリット③自己肯定感アップや成功体験を積める
習い事を続けていると、「検定級が上がる」「表彰される」「試合に勝つ」など、成功体験を積み重ねることができます。こうした経験は子どもの大きな自信となり、自己肯定感の向上につながります。
自己肯定感が高まると、「自分ならできる!」という前向きな気持ちで物事に取り組めるようになります。
中学受験という大きな壁に直面しても、習い事での成功体験が心の支えとなり、困難にチャレンジするのを後押ししするでしょう。
習い事を続けるデメリット
デメリット①時間が削られる
習い事を続ける一番の課題は、勉強時間が削られることです。移動時間や自主練などの時間を含めると、想像以上にまとまった時間が失われます。
習い事と塾のスケジュールが重なるケースも少なくありません。特に5年生以降は通塾日数が増えて、両立の難易度は一気に上がります。習い事を優先する場合、選べる塾が限られてしまうこともあります。
スポーツ系の習い事では休日の試合が大きな負担になります。塾でも模試や特訓講座が週末に入るため、スケジュールの調整が非常に困難になります。
デメリット②疲労
特にスポーツ系の習い事は、どうしても体力を消耗します。練習や試合の後はクタクタになり、机に向かう気力が残らないことも珍しくありません。
「今日は疲れたから、勉強は後回しでいいや…」となってしまうと、学習習慣が崩れてしまうリスクもあります。
中学受験と習い事を両立させるか?/いつまで続けるか?を判断する5つの基準
習い事を続けるかどうかを判断する上で、親の判断だけで無理やり辞めさせるのは注意が必要です。
必ずしも習い事を辞めたからといって、受験勉強に集中できるとは限りません。
習い事を続けるかどうかの判断基準は次の5つです。
- 子供の意欲
- 子供の様子
- 志望校のレベルと学力差
- 塾のスケジュール
- 習い事の将来性
1.子供の意欲:親の「想い」を優先させるのはNG
子供が習い事に意欲を見せている場合は、慎重に判断しましょう。
例えば、「楽しんで取り組んでいる」「笑顔で活動している」「自主的に活動している」などが見られるときは、習い事が子どもの成長に良い影響を与えている証拠です。
また、「この級まで頑張りたい」「この大会まで挑戦したい」といった目標を掲げている場合も、簡単に辞めさせるのではなく、尊重してあげたいポイントです。
ただし、あまりに習い事にのめり込みすぎると、6年生の追い込み期でも、勉強に専念できないリスクがあります。
子どもの意欲が旺盛であれば、完全に辞めさせるのではなく、頻度を減らすなど、バランスを工夫するのも大事です。
一方で、子どもの意欲が高くなく、実際には親の意向で習い事を続けている場合は、早めに見切りをつけることも選択肢の一つです。
2.子供の様子:負担が大きい時のサインを見逃さない
子供の様子を観察して、「本当に両立できているか」を見極めるのが大切です。親として、次のようなサインに注意しましょう。
- 疲れが抜けず、勉強に集中していない、イライラしている
- 就寝時間が遅れるなど生活リズムが乱れる
- 塾の宿題や模試の対策が十分にできない
このような状況が続くようであれば、両立が難しくなっているサインかもしれません。
3.志望校のレベルと学力差:模試判定から冷静に判断
志望校の模試判定は大きな目安になります。特に6年生になる前の段階で、模試の判定を冷静に見極めるのが大切です。
判定結果を基準に次のように整理できます。
・志望校の偏差値をクリア(上回っている) →習い事と勉強の両立は十分に可能。無理なく続けられるでしょう。 ・志望校の偏差値から -5以内 →調整次第で両立が可能。習い事の回数を減らしながら、勉強とのバランスを工夫しましょう。 ・志望校の偏差値から -5以上
→ 習い事の中断を検討しましょう。勉強に専念しないと志望校の合格が遠のきます。
4.塾のスケジュールから:5年生からは塾優先のスケジュール管理
5年生あたりから通塾回数が一気に増えるので、ここが大きな転機になります。平日の授業に加えて、週末には模試や特訓講座が入り、塾中心の生活へとシフトしていきます。
習い事と塾のスケジュールが重なり、両立が難しくなるケースも少なくありません。もしもスケジュールがぶつかるようであれば、思い切って中断を検討することも必要になってきます。
5.習い事の将来性:自己アピール型入試の活用を考慮
英会話やプログラミングといった習い事は、受験に直結することがあります。実際に、特色入試で英語やプログラミングを試験科目として課す学校も増えてきています。
そのため、中断せずに続けていくことが、受験そのものの強みになるケースも少なくありません。
さらに、自己アピール型入試では「これまで打ち込んできたこと」を伝える場面があります。長年取り組んできた習い事は、努力の証として説得力を持ち、自己PRの大きな材料になります。
一方で、芸術やスポーツといった習い事は「将来もずっと続けたい」と考えることが多く、簡単にやめる決断ができません。
中学受験を優先するか、将来の夢につながる活動を優先するか、親子でじっくり話し合うことが大切です。
受験勉強と習い事の両立を実践する3つのポイント
習い事と受験勉強を両立させるためのポイントは次の3つです。
- 平日1〜2回に絞る
- あくまでも気分転換として捉える
- 6年生からは中断も検討する
家庭でしっかりと方針を決めて、後悔のない選択をして下さい。
1.平日1〜2回程度に絞る:あらかじめ時間を想定してスケジュール管理
あらかじめ回数を決めて、習い事で拘束される時間を想定したスケジュールを組みましょう。
まずは、平日1〜2回程度に調整してください。通塾の曜日は変更が難しいため、あくまでも習い事の曜日を柔軟に調整しましょう。
週末は特訓講座や模試、学校見学などで予定が埋まりやすいため、この場合は「受験優先」で判断するのが得策です。
2.気分転換と位置付ける:習い事の成果は度外視して心理的負担を軽減
習い事はあくまでも「気分転換」と位置付けましょう。
特にスポーツでは「試合に勝ちたい」、芸術系では「コンクールで入賞したい」といった目標を持ちやすいものですが、結果は度外視する割り切りも重要です。
結果を追い求めすぎると心理的な負担が大きくなり、「勉強も大事だけど、勝ちたい気持ちもある…」という葛藤を抱えてしまいます。これこそストレスの原因になります。
3.小学6年生からは断ち切る:遅くとも6年からは受験に一本化
小学6年生からは、習い事を一旦中断することを視野に入れてください。
大好きな習い事ほど夢中になりやすく、勉強よりも優先してしまう可能性があります。
さらに、6年生になると、スポーツなどでは大事な大会が増えて、試合と受験勉強の両立は非常に難しくなります。特に団体スポーツだと、試合を休むとチームメイトにも迷惑をかけてしまいます。
親が責任を持って「今は受験を優先する」と決断することも大切です。
子供はなかなか先を見通せませんが、合格して中高一貫校へ進めば、高校受験がないので、思う存分、習い事に打ち込める時間があります。
我が家の体験談:中学受験とサッカーの両立をめぐる選択
最後に、中学受験とサッカーの両立で悩んだ我が家の体験談を紹介します。ぜひ、参考にして下さい。
小学1年生〜小4:サッカーが最優先だった日々
長男は小1からサッカーを始めました。試合や練習に明け暮れ、完全に「サッカー中心」の生活でした。
中学受験を見据えて、小4から通塾も始めましたが、この頃は、明らかにサッカー>受験勉強でした。
親としても、子供のサッカーを応援するのが楽しくて、「まだ両立できるかな」と甘く考えていたところがあります。
小5:塾が本格化、両立の壁に直面
小5になると、塾の授業だけでなく、模試やクラス分けテストも増え、勉強の負担が一気に大きくなりました。同時に、サッカーでも中心選手になり、ますますサッカー熱が高まってきました。
本人の中では「サッカーもやりたい、でも勉強もやらないといけない」という葛藤が生まれ、かなりのストレスだったようです。
塾の授業だけならまだしも、「宿題」や「クラス分けテストのための勉強」にまで手が回らなくなってきたのが現実です。
話し合いの結果、長男の志望校なら、必ずしも大手塾でなくても目指せると判断。そこで転塾を決意しました。地元の塾に移ったことで、 サッカーと勉強の両立が少し楽になったようです。
小6:受験優先へ、サッカーを一旦中断
小6からは受験に専念するためにサッカーを中断しました。本人には小5の頃から繰り返し話をしていたので、納得した上での決断でした。
最初は「やっぱりサッカーを続けたい」という気持ちもあったと思いますが、勉強一本に絞ったことで余計なストレスが減り、集中して受験勉強に取り組めたようです。
無事に第一志望校から合格を頂き、受験が終わるとすぐに、サッカーチームに復帰して、残り短い時間ですが、チームメイトとサッカーを楽しみました。
今振り返ると、小6から受験に専念したのは正しかったと思います。
最後の最後の難しい決断は、小学生の本人だけではできません。やはり親が責任を持って方向性を示すことが大切だと痛感しました。
中学・高校:サッカー再開、そして気づいたこと
中学進学後はクラブチームでサッカーを再開。高校受験がないため、強豪クラブチームで思う存分サッカーに打ち込めました。
高校では、学校のサッカー部で続けました。進学校のサッカー部だけあって、勉強とサッカーを両立するのが当たり前の雰囲気があり、充実していたようです。
我が家の結論:親子の納得感を持っておくこと
最初は「ある程度なら両立できるだろう」と思っていましたが、実際にはそう甘くありませんでした。
それなりのレベルの中学を目指すのであれば、(もちろん例外的に両立できる子もいますが) 本格的な両立は難しいと思います。
だからこそ、「習い事は気分転換程度に続ける」「このタイミングで区切りをつける」などを、親子でしっかり話し合って納得しておくことが大切だと感じました。