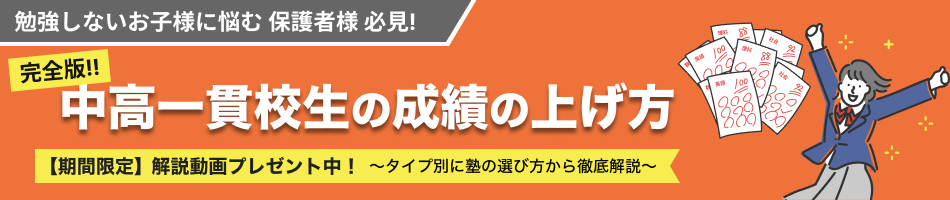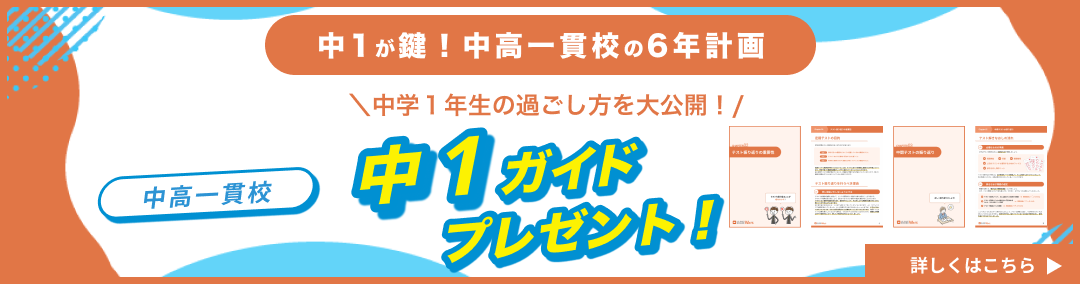着実に数学の応用力をつける方法

応用力がない人が応用力をつけるためには、
「類題を解く」事が必要です。
参考書の問題の類題がどのようなものかを知らないと、
参考書の問題の知識から、類題に応用して解けません。
ここで「類題を解く」というのは、
「この問題は、あの参考書のあの問題の類題だ!」
ということを把握しないとただ「問題を解く」になってしまいます。
模試でも過去問でもいいですが、解けなかった問題で、
「なんか見たことあるなこの問題。。」と思ったら、
すかさず数学の参考書やテキストを開いて、
同じような問題を探してください。
探せたらその問題の類題と見なします。
続いて、参考書の問題と解けなかった類題を比べてみてください。
そもそも、参考書の問題が解けてない場合は、
応用力以前の話なのでここでは無視します。
類題はなぜ解けなかったのか、参考書の問題と何が違うのか、
どのような考え方が必要だったかなど、
参考書の問題と類題のギャップを埋めるためには、
どうすればいいのか考えます。
また、受験生は参考書の問題のそばに類題の出典を書き加えます。
第3回全統記述3(2)とか、2010早稲田政経3って感じで書いておくのがおすすめです。
そして、参考書の問題を解くときに類題を意識してください。
類題を解けるようにすることを考えることで、
参考書の問題の応用を意識することができます。
参考書に類題が載っている場合、類題を頭のなかで解いてください。
方針を立てるだけです。解けたら回答をさらっと見て終わりです。
頭のなかで解けなかったら実際に解いてみてください。
例題で学んだ知識を、類題で使えるかどうか試すことが大切です。
面倒くさいかもしれませんが、これをやるかやらないかで、
類題に対する応用力がかなり変わります。
合わせて読みたい
投稿者プロフィール
-
中高一貫校生の定期テスト対策から大学受験・内部進学までをトータルサポートする個別指導塾。
中高一貫校用教材に対応することで各中高一貫校の定期テストの点数に直結した指導を行います。
低料金で長時間指導が受けられるため、家で勉強できない中高一貫校生でも塾の指導時間内で成績を上げることが可能です。
英語、数学をメインに指導を行っています。
最新の投稿


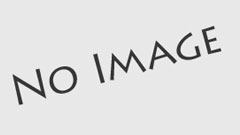 一貫教育コンパス2024年10月19日“正解”がないからこそ!保護者へのアンケートから分かる、 中高一貫校生の夏休みを有意義に過ごす方法
一貫教育コンパス2024年10月19日“正解”がないからこそ!保護者へのアンケートから分かる、 中高一貫校生の夏休みを有意義に過ごす方法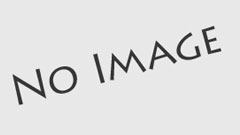 一貫教育コンパス2024年10月19日中高一貫校出身の海外留学経験者による匿名座談会!~私の留学はこうでした~
一貫教育コンパス2024年10月19日中高一貫校出身の海外留学経験者による匿名座談会!~私の留学はこうでした~