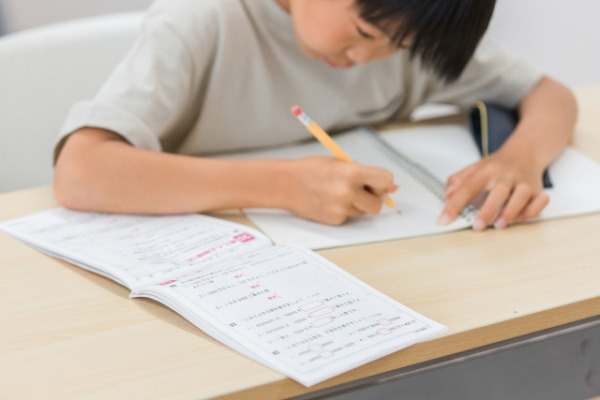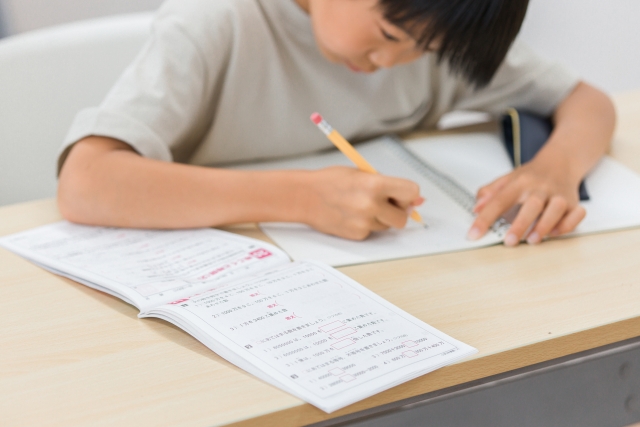中学受験を初めて経験するご家庭にとっては、いつから受験の準備を始めたらいいのか分からないかも知れませんね。
中学受験塾の受験用カリキュラムは、小3の2月から始まります。つまり、このタイミングで準備を始めるのが一般的です。
この記事では、中高一貫校教師で、自身の2人の子供も中学受験を経験したライターが、中学受験の準備を始めるタイミングと受験までの大まかな流れを解説します。
このページの目次
中学受験の準備を始めるタイミング:塾のカリキュラムが始まる小学3年生の2月が目安
中学受験塾が始まる「小学3年生の2月」から約3年間の準備期間を取るケースが多い
中学受験の準備を始めるのにベストなタイミングはズバリ、小学3年生の2月です。理由はシンプルで、中学受験塾のカリキュラムが小3の2月に始まるからです。
このタイミングで塾に入って、中学受験の準備を始めるのが理想的です。
中学受験が2月に終わることもあり、塾の新学年は2月から始まります。標準的なカリキュラムだと、
- 小4〜小5(あるいは小6の1学期):中学受験内容の範囲学習
- 小6(あるいは小6の2学期):発展問題や入試問題の対策
のスケジュールで進みます。
ただし、入塾前にもするべきこともありますし、小3の2月を過ぎてから準備を始めることも可能です。
中学受験の準備期間を十分に取るのは、ハイレベルかつ加熱感があるから
中学受験の学習内容は中学生レベル
中学受験の準備を始めるにあたり、まずは前提条件を押さえておきましょう。
中学受験では、「中学校で習う内容を小学生がどうやって解くか?」が問われます。
つまり、小学校で習う事だけでは不十分で、中学校で習う事まで勉強しなければいけません。
小学生にとっては、ハイレベルな内容を勉強する必要があるので、十分な準備期間が必要になるのです。
例えば、算数では、中学で解く問題を公式を使わずに、特殊算で解いたり、国語では中学レベルの文章題が出題されます。
中学受験は首都圏を中心に加熱気味
首都圏を中心に、中学受験はたいへん人気で、加熱気味です。中途半端な準備だと、志望校に合格できないところか、「全落ち」もあるのが現実です。
本来なら、中学生が高校受験のために払う犠牲(=受験勉強)を前倒しで、小学生で経験ことになります。小学生にとっては負担が大きく感じるかもしれません。
【中学受験と高校受験のどちらが大変かを解説した記事はこちらから】
準備期間の長さは家庭次第!だからこそ家庭の方針が大事
3年間の準備期間が標準的と言うと、小学生にとっては、「長い」と感じる事でしょう。
家庭の方針や子供の適正によって、中学受験で目指す方向性は様々です。
何が何でも難関校を目指すケースから、必要以上に背伸びをしない「ゆる受験」まであります。
他人と比べたり、塾の思惑に流されたりしてしまうと、親子で必要以上に疲弊する可能性があるので、気を付けたいですよね。
中学受験の全体像|小1〜小6学年別に学習内容・志望校選定・親のサポートを解説
小学1年生〜小学3年生:学習習慣の確立、基礎固め、体験重視で中学受験の準備
受験勉強をスムーズに進めるために、入塾前にしておくべき準備があります。
①学習習慣の確立
日常生活に勉強を組み込んで、学習習慣を確立しましょう。塾に入ると多くの課題が課されます。
その上で、集中して授業を受けられるようにしましょう。塾は集団授業が基本です。
まずは小学校の授業をきちんと受けて、毎日30分でいいから宿題をするように促しましょう。
②基礎固め
基礎固めがとにかく大事です。
受験は思考力重視と言われますが、基礎学力がないところには思考力は身につきません。「計算」「漢字」「読書」に、しっかり取り組んでください。
- 計算:ドリル問題集などを使って早く正確に
- 漢字:ドリル問題集などを使って丁寧な文字で
- 読書:興味の赴くままにたくさん読書をする。幼い頃からの読み聞かせも有効
③体験重視
様々な体験が大事です。
体験が豊富だと、受験勉強を通じて習うことと、自身の体験がつながって、理解が深まります。
例えば、家族で車に乗っている時に、「時速60kmだよ」と言ってスピードメーターを見せると、実際の速さが体感できます。算数の時速の問題を解くときの実感につながります。
公園で遊んでいると季節の移り変わりを感じます。秋風を感じた経験があれば、国語の問題で「風が心地よく感じた」といった記述があっても、イメージが湧いてきます。
動物園や博物館などに行くだけが体験ではありません。外遊びやお手伝いなどを通して様々な体験をさせましょう。
小学4年生〜小学5年生:塾カリキュラムの勉強を!親も子供の勉強をサポート
①中学受験の出題範囲の学習
中学受験で出題される内容の学習を進めるのですが、実際は、小学校で習うことだけでは対応できません。
その意味では、小学校の勉強中心で受験に臨むのは現実的とは言えません。
塾では、小学4年生で小学校で習う内容を先取りして、小学5年生から、中学受験ならでは内容(特殊算や中学レベルの内容)を勉強します。
この2年間で中学受験の出題範囲を学習するので、この時期は、塾のカリキュラムに合わせて勉強しましょう。
「中学受験は親の受験」と言われることがありますが、子供の学力だけでなく、親のサポート体制が大事になってきます。
親は子供の勉強を伴走する気持ちが大切です。
もちろん、勉強を教えられることに越したことはありませんが、親も子供の勉強に興味を持って一緒に学ぶ姿勢を持ちましょう。
《親のサポート/関わり方の実例紹介》 我が家の2人の子供も中学受験をしましたが、私自身も子供の受験には積極的に関わるようにしていました。 特に、塾で習ったことを理解できているか確認していかないと、塾の授業がわからないまま過ぎてしまいます。これでは成果が上がりません。 もちろん、親が子供の勉強を教えてあげれれば良いのでしょうが、それぞれ事情も異なります。 「教えないといけない」と意気込まないでも、「一緒に楽しみながら勉強する」という気持ちがあれば十分です。 私も子供の問題を一緒に解いていましたが、正直に言うと、分からない問題がいくつもありました。 こっそりと仕事の休み時間を利用して考えたりしたものです。 「子供もこんなに難しいことを勉強しているんだ」と分かると、冷静に受験に関われたと思います。
②子供に合った志望校選び
勉強と並行して、志望校選びを開始します。小6からは忙しくなるので、この時期から始めましょう。
学校説明会・文化祭・体育祭など、実際に学校に足を運んで、子供に本当にあった学校を探していきます。
「ここに行きたい!」と子供が憧れる学校が見つかれば、それが一番のモチベーションです。子供にとって、中学受験が「自分事」になれば、厳しい受験も乗り越えることができるでしょう。
【私立中学校(中高一貫校)の選び方に関する記事はこちらから】
③家族の役割分担・生活リズムの維持
小5くらいから、塾の勉強が本格化してきます。通塾日が増えて、週末にはクラス分けテスト、学校見学などなど。
帰宅が遅くなったり、勉強が難しくなったりで子供の負荷が大きくなります。
「勉強は誰が教えるのか?」「帰宅が遅くなった後の生活リズムをどうするか?」など親の関わりが求められるので、役割分担を明確にしておくと良いでしょう。
小学6年生:志望校対策が本格化!生活を完全に中学受験モードにシフト
①発展問題・入試問題演習
小6(あるいは夏休み終了時)で、塾のカリキュラムは範囲学習が終わり、発展問題や入試問題対策に入っていきます。
遅くても小6からは、全てを断ち切って受験に全集中する覚悟が必要です。
もちろん、親も子供の勉強にとことん付き合う覚悟を持たなければいけません。
②受験校の決定
これまでに見学してきた学校から、実際の志望校(本命校と併願校)を決定します。志望校が固まると、これからの勉強の方針が固まってきます。
小6の9月から志望校の過去問対策を始めて、合格に向けた勉強が佳境を迎えます。
また、チャレンジ校や安全校を含めた受験校を決めていくことになります。
特に、首都圏入試では、合否によって出願校が前日まで変わることもあります。
何通りかの受験パターンを想定しておくだけでなく、出願期間、合格発表、手続期間などの日程をしっかり確認してください。これは完全に親の役目です。
その際に、「全落ち」してしまう受験はおすすめできません。子供にとっては、「自分は全部落ちた」という劣等感を感じてしまうものです。
【偏差値の低い私立中学にいく価値があるのかに関する記事はこちらから】
入塾するベストなタイミング:小学3年生の2月、または季節講習を利用する
中学受験対策は塾のカリキュラムを活用する方が効率的です。ほとんどの家庭は塾で対策をするはずですが、ここからは、入塾のタイミングを解説します。
小学1年生〜小学3年生:軸足は家庭学習、塾で勉強する前の準備期間
この時期は、基本的には塾は不要です。
勉強の軸足は家庭において、塾の勉強のための準備期間に充てましょう。「学習習慣の確立」「基礎固め」「体験重視」を意識するとよいです。
サピックスのような有名中学受験塾の入室テストのために、塾に通うケースもあります。
小学4年生〜小学5年生:早めに入塾して環境に無理なく慣れるのがベスト
中学受験カリキュラム
小学3年生の2月から、受験用カリキュラムが始まります。この時期からは、なるべく早く入塾するのをおすすめします。
いきなり塾に通わせようとしても、子供が戸惑うかもしれないので、低学年からの準備が大事になってきます。
塾も最初はゆっくりと始まります。課題も少なめで、クラス分けもそこまで細分化されていません。
早く始めて、無理なく慣れていくのがベストです。
春期・夏期・冬期講習
春期・夏期・冬期講習では、それまでの学習内容の復習をします。
受験用カリキュラムが始まるのが小学3年生の2月ですが、このタイミングを逃した人は、季節講習から入塾しても良いでしょう。
例えば、新小5の春期講習で小4の復習をします。小4で入塾していない人でも、春期講習からだとスムーズに始めやすいです。
個別指導・家庭教師
クラス分けテスト対策や塾の課題をこなすために、個別指導や家庭教師を活用するケースもあります。
あくまでも家庭の方針次第ですが、他人と比べたり、塾の思惑に流されて、疲弊や課金に繋がらないようにしましょう。
小学6年生:新規入塾は困難に・手遅れにならないように早めの準備を
小学6年生になると、大手塾では受験用カリキュラムが終わり、発展問題、入試問題演習に入っています。
これまでに習ったことが前提に授業が進むので、ここからは入塾できない可能性が高いです。
それでも入塾したい人は地元小規模塾などが現実的な選択肢となります。
個別指導・家庭教師
志望校対策のために個別指導や家庭教師を活用するケースもあります。
親のサポートにも限界があります。
それでも志望校合格を勝ち取るためには必要かもしれません。あくまでも家庭の方針次第です。
中学合格後:基本的には塾は不要も、難関大志望の先取り学習で活用するケース
受験が終わった後では、基本的には塾は必要ありません。学校側も塾で勉強を進めておくことを想定していません。
しかし、受験が終わった開放感から、全く勉強しなくならないように気をつけましょう。せっかく身につけた学習習慣は必ず維持してください。
【中学受験の終わった後の過ごし方を解説した記事はこちらから】
難関大志望の生徒は、鉄緑会・SEGなどで大学受験の準備を始めるケースもあります。
また、学習習慣を維持しながら学校の勉強をサポートする個別指導塾を検討しても良いでしょう。
『中高一貫専門 個別指導塾WAYS』は、中高一貫校のカリキュラムに合わせた指導が強みの個別指導塾です。 WAYSでは、「中高一貫校は授業の進度が速く、難易度が高いため、ついていけなくなる前に塾で対策しておきたい」といった理由から、中学1年生の4~5月から入塾する生徒も少なくありません。 WAYSでは、「中高一貫校 新中1スタートガイド」を無料で配布していますので、ぜひダウンロードしてください。