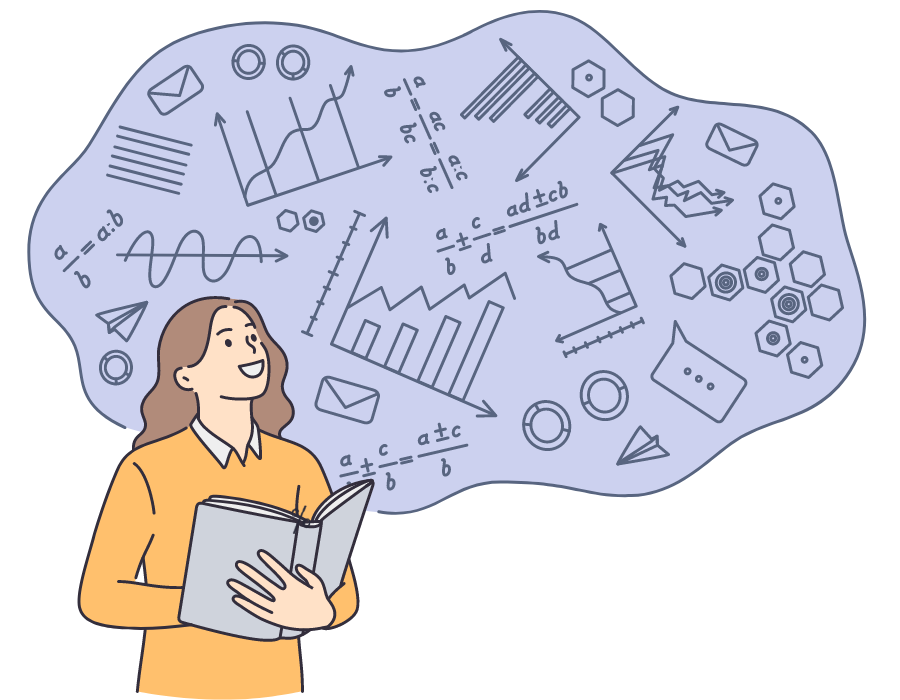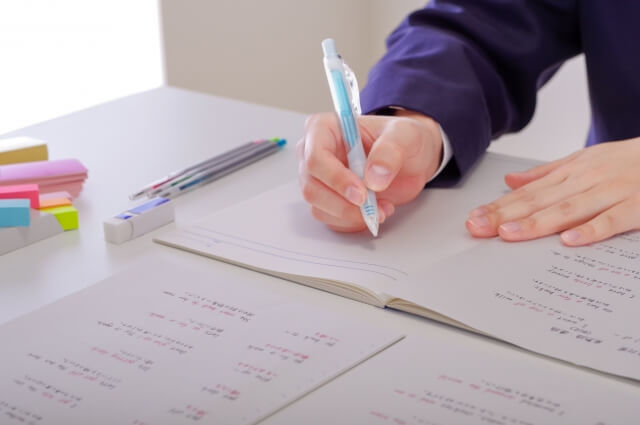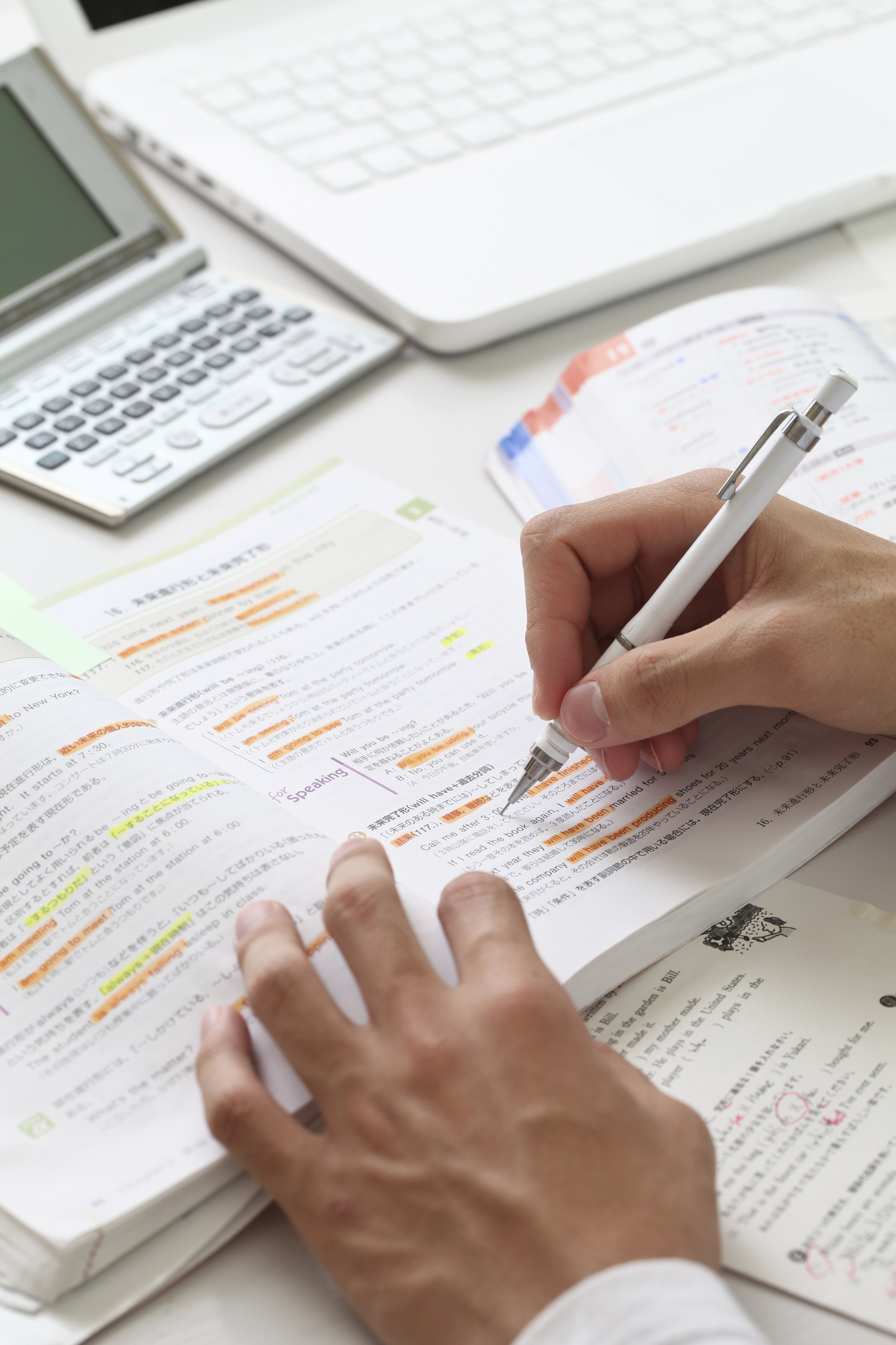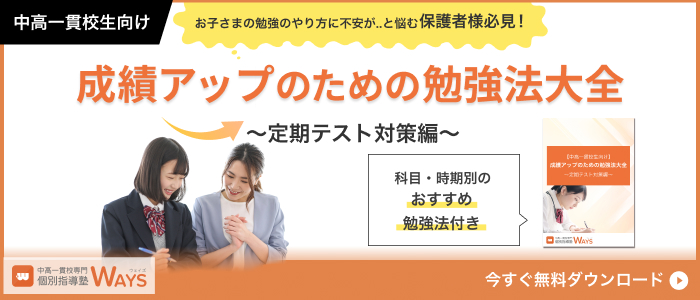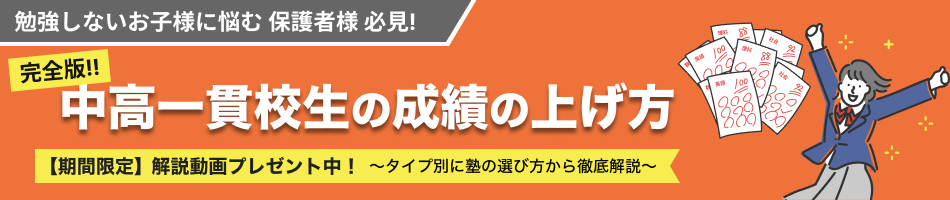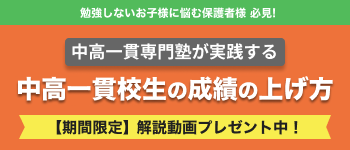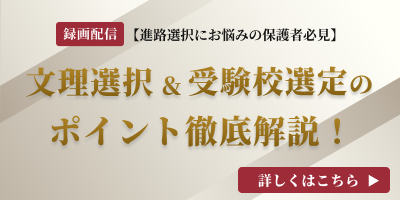参考書等の問題の知識だけでなく類題に対応する応用力も大切

- 大学受験は暗記するだけで合格できます。
- 数学は暗記です。青チャート例題を覚えれば東大受かります。
- 受験英単語2000個覚えるだけで偏差値70とれます。
- ○○の参考書やれば偏差値60切りません
多くの場合、上に書いてあることを実行しても、
目指している結果は得られません。
所詮は極端な1つの成功例にすぎません。
しかし、これらの主張はかなり雑ですが、
前提となる学力を持っている場合、良い結果を生み出すことがあります。
では、十分な結果を得るために必要な
「前提となる学力とは何か」というのを
考えて行きましょう。
前提知識が必要
まず、土台となる知識が必要です。
これらの方法を小中学生がやっても十分な結果は得られません。
青チャートを覚える、受験英単語を覚える前に、
四則計算、基本的な公式、中学生の英単語など、
基礎的な知識を頭に入れていなければ、東大合格や偏差値70は取れません。
類題への対応力
では、土台となる知識を覚え、青チャート、英単語2,000個覚えたとします。
勉強の計画をしっかり立てて、それを実行していれば、
ここまで達成するのは、時間がかかるだけで難しくありません。
しかし、上述の通り、これだけでは十分な結果は得られません。
類題への対応力、つまり応用力が必要です。
試験に青チャート例題、英単語2,000個がそのまま出るわけではありません。
覚えてきた知識を問題によって応用しなければなりません。
試験では、問題設定が複雑になっているため、
参考書に載っている知識を利用する類題に気づけないことがあります。
普通、参考書の問題は、多くの類題に対応できるような問題形式になっており、
ごく一部のすでに応用力のある人は類題に対応できますが、
ほとんどの人は応用力がないため、少しひねった類題への対応出来ません。
まとめ
上の主張は、達成のための最低限の知識量を示していると考えましょう。
では応用力のない人はどうすればよいか。
応用力をつけるか、知識量でカバーするかのどちらかです。
英単語で言うと、
似ている形から意味を推測できるようにするか、
単語帳の見出し単語以外の細かな単語も全て覚えるか、
のどちらかです。
理系科目の場合、個人差はあるにしても、ある程度の知識を詰めたら、
点数につなげるには応用力をつける方が楽ですし、
他の科目への汎用性も高いので、応用力をつけるのをおすすめします。
投稿者プロフィール
-
中高一貫校生の定期テスト対策から大学受験・内部進学までをトータルサポートする個別指導塾。
中高一貫校用教材に対応することで各中高一貫校の定期テストの点数に直結した指導を行います。
低料金で長時間指導が受けられるため、家で勉強できない中高一貫校生でも塾の指導時間内で成績を上げることが可能です。
英語、数学をメインに指導を行っています。
最新の投稿