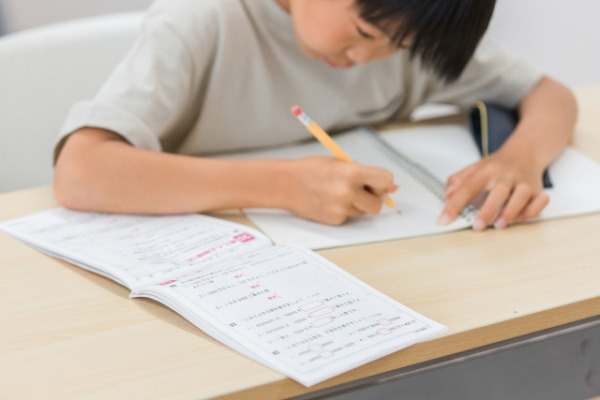中学受験では、模試の偏差値が45前後だった子が、50台後半の私立中学に合格するなど、「逆転合格」が起こるケースがあります。
「憧れの学校にどうしても通いたい」「高偏差値の学校に受かるか試してみたい」などの理由で、逆転合格を狙う方も少なくありません。
しかし、なんとなく挑戦するだけでは、厳しい結果に直面する可能性が高いでしょう。
中学受験で逆転合格を狙うのであれば、お子様に合わせた戦略が欠かせません。
逆転合格を実現するためになにをすべきかを、
- 子ども本人のやる気を引き出す
- 中学受験でありがちな5つの弱点(勉強のクセ)を解消する
- 志望校の過去問分析、やりこみを行う
以上3つの観点から、徹底解説します。
このページの目次
漫画でも話題だが、逆転合格の可能性は決して高いとは言えない
中学受験の逆転合格といえば、「ジャイアントキリング」という言葉が気になる方も多いのではないでしょうか。
ジャイアントキリングは、中学受験を題材にした人気漫画『二月の勝者』で、登場人物が逆転合格を起こした際に注目を集めた言葉です。
基本は偏差値どおりの結果に。戦略的に可能性を高める必要がある
ジャイアントキリングのような劇的なストーリーに憧れるかもれませんが、その事例は少なく、厳しい道程といえます。
筆者の娘が中学受験をした際も、周囲で逆転合格を狙うケースがありましたが、多くの人が偏差値水準の学校に収まっていました。
大多数の人が偏差値どおりに合格する理由は、模試の偏差値が信頼性の高いデータであるためです。
例えば、関西圏の私立中学校では、自己推薦入試の資格として、「五ツ木駸々堂模試」で偏差値〇〇以上という条件が設けられている学校もあります。
小学校の内申点とともに受験資格として設定されるほど、模試の偏差値は信頼に足るデータであるといえるでしょう。
しかし、模試の偏差値は、毎回一定ではありません。
模試の出題範囲や、お子様のコンディション、母集団の学力など、さまざまな影響を受けて変動します。
お子様の状況に合わせて効率的に学習を重ねていけば、大幅な学力アップも夢ではありません。
逆転合格に近づけていけるように、入念に戦略を練ることが大切です。
「上振れ」に頼らない。逆転合格には、穴を埋めていく戦略的な勉強が必要
模試の偏差値に波があるお子様には、基礎の定着にムラがあると考えられます。
模試の成績が普段より上振れるのは、しっかり定着している分野や、得意分野が、運良く出題されたときでしょう。
上振れ時の偏差値程度までは、逆転合格の可能性も考えられますが、逆に定着が甘い分野や苦手分野が出ると、急落するケースも多くみられます。
逆転合格の可能性を高めるためには、乱高下する偏差値の波を落ち着かせる必要があります。
定着が甘い分野や苦手分野を減らせるように、一つずつ穴を埋めることを意識して、戦略的に勉強に取り組みましょう。
逆転合格に不可欠!子どもの「やる気」を引き出す4つの大切なアプローチ
子ども本人が前向きでなければ、逆転合格の実現は極めて困難
逆転合格を達成できるほどの濃密な学習を実現するためには、お子様自身のやる気が欠かせません。
なぜなら、やる気がある状態で勉強すると、やる気のないときより学習量や効果が著しくアップするからです。
やる気がどれだけ重要であるかについて、筆者の娘の話を一例としてご紹介します。
小学6年春までの筆者の娘は、中学受験で地元の学校から離れたい気持ちはあるものの、特定の学校への憧れや上昇志向はそれほどありませんでした。
そのため、親中心で志望校を選んでいた頃の娘は、勉強に気が乗らず、「親がすすめるなかでは、この学校がよさそう」と受け身の姿勢で選んでいた印象です。
そこで、筆者はネットの書き込みや偏差値表から選ぶことをやめ、身の周りのOBに尊敬できる人が多い学校の、オープンキャンパスに足を運んでみたのです。
すると、娘は一気に心変わり。本人の口から「絶対、ここに行きたい!」と明確な言葉が出てきました。
そこからは、勉強への意欲も大幅にアップ。見違えるようにいきいきとした受験生になりました。
以降も、文化祭やクラブ体験などに行くごとに、学校への憧れが強くなっていき、勉強への意欲も高まっていったのが印象的です。
子ども自身が心から行きたいと願う気持ちは、受験において大きな原動力になるのだと感じました。
このように、お子様が受験を自分ごととして捉え、しっかりと向き合えるようになると、やる気がアップします。
お子様のやる気を引き出すアプローチとして、以下の4点を意識してください。
- 憧れの学校に足を運び、実際に魅力を体感させる
- 小さなゴールで達成感を定期的に感じさせる
- 些細な努力や変化に気づいて認めてあげる
- 自分で決めた勉強をやり遂げることで達成感を持たせる
詳しく解説します。
1.憧れの学校に足を運び、実際に魅力を体感する
逆転合格という険しい道を選ぶご家庭には、それぞれ憧れの学校があるでしょう。
しかし、強く憧れているにもかかわらず、学校自体をきちんと知らないケースは珍しくありません。
学校の知名度や偏差値だけを原動力に、過酷な受験勉強を乗り越えるのは難しいものです。
やる気を引き出すためには、勉強の対価になるほど魅力的な学校だと、お子様自身に体感させてあげてください。
筆者の娘が憧れの学校に出合ってやる気が出たように、相性のいい学校と出合うことは大切です。
お子様の性格に合う校風の学校を選んだり、お子様が好きそうなクラブ体験をしてみたりと、魅力を味わえる機会をつくりましょう。
2.小さなゴールで達成感を定期的に感じさせる
「志望校合格」というゴールは、とても遠く大きく、受験が終わるまで達成できません。
ずっと達成感を得られない環境では、勉強のやる気を持続しにくいものです。
やる気を維持するためにも、達成感が得られる環境づくりを心がけましょう。
達成感を獲得する方法としておすすめなのが、小さなゴールを設けることです。
クリアしやすい小さなゴールであれば、定期的に達成感を得られるため、モチベーションを維持しやすくなります。
ゴールというと、「模試の偏差値+5」「テストで100点獲得」など、高めのハードルを設定したくなるかもしれません。
しかし、そうしたゴールはなかなか達成できないうえ、達成するまでに挫折してしまう恐れもあります。
小さなゴールは、「計算問題は1日10問必ず解く」など、達成しやすいものにしましょう。
毎日達成できると積み重ねがどんどん増えるため、自信もつきやすくなります。
3.些細な努力や変化に気づいて認めてあげる
普段しないことを1つでもやってみると、達成感が味わえるものです。
しかし、親がそれに気づかなかったり、当然のこととして流したりすると、やる気を削ぐ原因になってしまいます。
大切なのは、些細な変化を見逃さないことです。
以下のような動きがないかを、細やかにチェックしてください。
- 普段していない内容の勉強をしている
- 普段より早く勉強机に座った
- 普段より長く勉強している
- 普段より正解数が多い
- 普段していない解き直しをしている
- 普段より丁寧に解き直しをしている
普段と違う動きがあるかどうかに目を配っておくと、お子様のやる気の変化にも気づきやすくなるでしょう。
子どもは大人が気づいてくれることに喜びを感じ、それを認めてもらえることでやる気につながります。
認めることは重要ですが、過剰に褒める必要はありません。
「いつもちゃんと見てくれている」「認めてもらえている」という安心感、充足感を与えてあげましょう。
4.自分で決めた勉強をやり遂げることで達成感を持たせる
塾や保護者の方から出された課題をやり遂げるだけでなく、お子様自身に勉強メニューを決定させましょう。
なぜなら、ただやらされているだけの状態よりも、自分で決めた勉強をやり遂げたときのほうが達成感があるからです。
さらに、「決めた範囲が終わるまでは必ず勉強を続ける」というルールを設けてみてください。
決めた範囲の勉強をクリアすれば自由時間を確保できるため、効率的な勉強について考える効果も期待できます。
しかし、お子様自身に決定権を与えることが重要ですが、子どもが独断で勉強の内容や量を考えるのは難しいものです。
範囲と量を適切に設定するためにも、やはり大人のサポートは必須といえます。
親子で相談しながら本人に決めさせるか、塾で先生に相談するのが望ましいでしょう。
どちらにしても、決断は本人に任せることが大切です。
範囲と量の設定時には、小さなゴールを意識して、毎日達成できるボリュームに調整しましょう。
中学受験でありがちな5つの弱点(勉強のクセ)の見直し方
失点を招く勉強のクセは、お子様の弱点です。
何度も同じミスを繰り返してしまったり、いつまでも理解ができなかったりと、効率の悪い学習になってしまいます。
逆転合格の可能性を高めるために、一つひとつ弱点を潰していきましょう。
中学受験でよくみられる弱点は、主に次の5点です。
- ケアレスミスで点を落としている
- 応用問題は解けるのに、基本問題でつまずくことがある
- 理科・社会の失点が足を引っ張っている
- スケジュール管理が不十分
- 間違えた問題があっても、解説を読むだけで解き直さない
1.ケアレスミスでの失点は、原因を指摘してクセを直す
原因によって、対策が異なります。適切な対策をとるためにも、まずはケアレスミスの原因を分析してください。
ケアレスミスの原因1:字が汚い→見間違いしやすい字は要警戒
判読できない字を書いてしまったために、バツをつけられるケースは少なくありません。
また、計算問題を急いで解いていると、自分の書いた数字を見間違えて、計算ミスを起こすこともあります。
「0」と「6」、「田」と「由」のような見間違いしやすい字で、怪しい書き方をしている際は指摘してあげましょう。
とくに、数字や漢字は、正しく書けていなければ失点に直結するため、誰が見てもきちんと判読できるようにチェックを徹底してください。
ケアレスミスの原因2:途中式を書いていない→簡単な問題でも必ず式を書く
暗算はせずに、必ず途中式を書く習慣をつけてください。
簡単な問題ほど油断しやすく、ケアレスミスにつながる恐れがあります。
途中式を書いていると、見直しの際にもミスに気づきやすくなるため、確実に得点を稼ぐためにも途中式は必ず書いておきましょう。
ケアレスミスの原因3:問題の書き間違い→書き写した時点で必ずチェック
問題を書き写したら、その時点で書き間違えていないかどうかを必ず確認してください。
計算自体は合っている可能性が高いため、しっかり見直しをしても気づきにくいでしょう。
見直しのときにも、書き写しの間違いがないかを、確認するクセをつけてください。
計算前と計算後のWチェックができるため、入念に対策できます。
2.応用問題が解けても基本問題でつまずく場合は、基礎を最優先
得意分野をさらに伸ばすよりも、まずは苦手分野の基礎のマスターを最優先に考えてください。
たとえ得意分野の応用力が高くても、成績の波が荒いままでは、難関校への逆転合格の可能性を高めることができないためです。
苦手分野は、基礎を固めてから応用問題に着手するようにします。
具体的には、基本問題がすべて解けるようになるまで、間違えた問題を繰り返し解き直し、基礎を固めましょう。
基礎を固めてから応用問題に手をつけてみると、以前は解けなかった問題の正答率もアップして、驚くはずです。
3.理科・社会は小学6年の夏休みに基礎を総復習。応用は小学6年後半に
算数・国語に特化していると、理科・社会が疎かになってしまうケースも見受けられます。
「終盤の追い込みで対応できる」という説もありますが、これは基礎が定着している前提の話です。
基礎が定着していない状態で最後に詰め込もうとしても、膨大な範囲をカバーできるだけの時間はありません。
そこで、理科・社会は、小学6年の夏休みに、これまでの総復習を行い、しっかりと基礎を押さえましょう。
基本問題をきっちりと解ける状態にしておくことが目標です。
忘れている問題や間違えた問題は、解けるようになるまで解き直し続けることを忘れないでください。
基礎の定着には、塾で用意された夏期講習のテキストの活用が王道です。
一般的に、これまでの総復習ができるように設計されているためです。
夏期講習のテキストがない場合は、これまで使用してきたテキストの基本問題を解き直しましょう。
夏期講習が終わり、小学6年生の後半に入ってから、演習や応用問題に取り組みます。
基礎が定着しているため、グラフや図を読み取る問題や長文問題にも対応しやすくなります。
4.スケジュールは本人主導で考え、決定・実行させる
スケジュール管理をお子様が中心となって行うことで、自分の受験として向き合いやすくなります。
親や先生に決められたスケジュール通りに進めているだけでは、勉強が自分ごとに感じにくいからです。
「自分で決めた」という納得感があると、つらい勉強も最後まで乗り越えやすくなります。
本人主導にする場合のポイント1:子どもと一緒に考える
お子様主導でいきなり始めるのではなく、親子で一緒に考えるところから始めましょう。
いきなり一人でスケジュールを管理させても失敗しやすく、計画倒れになりやすいためです。
一緒に考えるときは、できるだけ本人の考えを尊重してあげてください。
自分の意思が汲み取られることで、自分ごととして捉えやすくなります。
お子様が意思表示をしない場合は、選択肢を与えて、選ばせてあげるとよいでしょう。
本人主導にする場合のポイント2:性格に合わせたスケジュール表作成を提案する
無理なくできるように、お子様の性格に合わせてスケジュール表作成を行いましょう。
スケジュール表の作成自体が面倒だったり、苦手に感じたりする子も少なくないため、スケジューリングへの苦手意識をなくすことが大切です。
<書くことが好きなお子様の場合>
自分の好きなように書かせてあげてください。
お気に入りのスケジュール表に仕上がると、それだけでモチベーションが高まりやすくなります。
使い勝手の面で気になる部分がある場合は、よりよくするための提案として、改善点を伝えるとよいでしょう。
<書くことが苦手なお子様の場合>
保護者の方がスケジュール表のフォーマットを用意したほうがスムーズです。
ストレスにならない方法で進めると、スケジュール管理への抵抗が和らぎます。
内容はお子様の意見を聞き入れながら埋めるなどして、お子様自身の考えを尊重して作成してください。
「朝小プラス」が提供している書き込み式のスケジュールシートは、中学受験に適したフォーマットに仕上がっていて使いやすいでしょう。
本人主導にする場合のポイント3:余裕をもたせたスケジューリングに導く
お子様がタイトなスケジュールを立てた場合は、あえて減らすことを提案したほうがよいでしょう。
やる気のあるときに立てたスケジュールは、無謀な内容になりがちだからです。
無理なスケジュールがストレスになると、かえって勉強意欲を低下させる原因になります。
保護者の方の配慮がお子様に伝わることで、お子様からの信頼もより厚くなるでしょう。
5.間違えた問題は「解き直したほうが得」だと体感してもらう
解き直しは、最も効果的な学習方法といえます。
勉強で重要なのは、理解不足な部分を特定し、その理解を深めることであり、解き直しによってすべて解決できるためです。
間違えた問題と向き合わずに放置するのは、せっかく見つけた宝の山を通り過ぎるようなものです。
間違えた問題の克服こそが、逆転合格への着実な一歩となります。
解き直しに抵抗を感じるお子様は少なくありませんが、ポジティブに捉えられるように働きかけましょう。
解き直しを習慣化させる方法1:「解き直しをしたほうが得」というマインドに導く
自分が得をするという考え方に導くと、積極性の向上が期待できます。
「しなければいけない」と思わせてしまうと、勉強が義務的になるためです。
間違いと向き合ったり、手間や時間がかかったりと、解き直しは子どもにとって負担を感じる作業です。
「放置するなんてもったいないよ」「これが解けたら次の応用問題も解けるようになるからお得だよ」などの声かけをして、解き直しのメリットを伝えましょう。
解き直しを習慣化させる方法2:解き直しによる達成感を与える
お子様がきちんと解き直したら、頑張ったことへの努力を認めて褒めてあげてください。
苦手なお子様の場合、やってみること自体が大きな一歩です。
嫌な作業でも、保護者の方に褒めてもらえるというメリットがあれば、原動力になります。
解き直しにメリットや達成感を与えることで、少しずつ向き合っていけるようになるでしょう。
そして、解き直しによる学習効果をお子様自身が体感できれば、習慣化させやすくなります。
逆転合格に最重要!過去問分析のポイントと具体的な勉強の進め方
難関校への逆転合格を狙うのであれば、志望校の過去問を分析し、徹底的にやり込む必要があります。
出題傾向や問題との相性は必ずチェック
過去問分析を行うことで、頻出単元や問題の形式、難易度、お子様との相性など、さまざまな重要ポイントが把握できるようになります。
小学6年後半の学習を効果的なものにするためにも、過去問分析はしっかりと行いましょう。
過去問分析のやり方
まずは、志望校での過去の出題傾向を調べてみてください。
数年分のデータから、どの単元から出題されているかを確認すると、頻出している単元の傾向が見えてきますので、丁寧に対策しておくとよいでしょう。
ただし、傾向はあくまで傾向であり、変わる可能性も十分にあります。
変わった場合でも慌てないように、お子様にその旨を伝えておくことも大切です。
記述問題の多い学校は、国語以外でも対応できるように慣れておく
近年は教科を問わず、記述問題を出す学校が増えています。
国語以外の教科でも、記述対策をしておきましょう。
記述問題は、ポイントをつかんでしっかりと答えることが大切です。
回答の方向性が合っていて、設問に対応した文末で答えられていれば、部分点でもしっかり稼げます。
過去問で繰り返し解き、その学校が求める回答に慣れておきましょう。
問題との相性がよい学校であれば、逆転合格を狙いやすい
塾の模試だと結果がふるわなくても、相性のよい学校なら、合格水準の点数を出せるケースも珍しくありません。
難関校であっても、お子様と相性のいい問題が出る学校は、点数を稼ぎやすくなります。
冠模試を受けると、志望校に似た形式の問題で力試しができるため、6年生の秋ごろに受けてみるとよいでしょう。
模試の結果を持参して塾の先生に相談をしてみると、お子様に合った学習アドバイスをもらえる可能性もあります。
過去問のやりこみはどうやる?具体的な勉強の進め方を徹底解説
受験終盤の勉強で、合否を分けるといっても過言でないのが、過去問のやりこみです。
少しでも効果的に、効率的に学習するための5つのポイントを解説します。
1.間違えた問題は必ずコピーをノートに貼って解き直し
過去問をただ解いて終了では、解けなかった問題を放置することになってしまうため、必ず解き直しをしてください。
解けなかった問題を解けるようになってこそ、逆転合格が現実味を帯びます。
間違えた問題のコピーを取り、そのコピーを解き直し専用のノートに貼ってから、解き直しましょう。
問題集は未使用同然の状態を保てるので、きれいな状態で繰り返し使えます。
解説や先生に頼らなくても解けるようになるまで、何度でも繰り返し解くことが大切です。
解き直しノートを作るのは親も子も大変ですが、努力の結晶として本番に力を与えてくれる存在となります。
2.最初は合格最低点から遠く離れていても気にしすぎない
解き直して問題に慣れていき、数年分の過去問で傾向をつかんでいくと、次第に点数が上がっていきます。
筆者の娘も、第一志望校の過去問を最初に解いたとき、苦手な算数はわずか3問しか正解できませんでした。
非常にひどい結果でしたが、繰り返し解き続けていくと、初見の年度の問題でも点数が上がっていくため、驚いたことを覚えています。
娘だけでなく、周りのお友達も同様のケースがみられましたが、各自しっかりと成果を上げていきました。
3.過去問の着手は早くても9月以降に
夏休みにしっかりと復習して基礎を固めておき、過去問は早くても9月以降に取り掛かることをおすすめします。
基礎が固まっていない段階で過去問を解いても、失点が多くなるだけです。
夏の段階でははまだ早すぎるため、過去問を解く時間を基礎固めに使ったほうが効率的だといえるでしょう。
4.全問解説の動画がある場合は購入する価値あり
過去問の全問解説の動画は、勉強の時短や効率化に役立つため、活用したほうがよいでしょう。
質問するためだけに塾に行く必要がなくなるうえ、質問待ちの列に並ぶ待機時間も減らせるためです。
質問に行くことにストレスを感じるお子様の場合も、気を遣わずに何度でも動画で繰り返し確認できておすすめです。
「中学受験専門塾 ジーニアス」では、算数の全問解説動画を無料公開しています。
志望校の動画がある場合は、活用するとよいでしょう。
5.最適な過去問対策ができているか不安があるときは、塾の先生に相談する
お子様に合った勉強の量や、方法がわからない場合は、塾の先生に相談するとよいでしょう。
過去問を使った学習は、塾や担当講師によって、方針が異なることがあります。
塾の方針に反した方法で学習すると、お子様が混乱したり、負担が大きくなったりする恐れもあるためご注意ください。
今のお子様の状態に合わせて、適切な講座を案内される可能性もあるので、先生のアドバイスを最優先で実行することをおすすめします。
逆転合格は、簡単にできることではないからこそ、入念なリサーチと親身なサポート、プロのアドバイスが重要です。
お子様、塾の先生と一丸となり、逆転合格を目指しましょう。