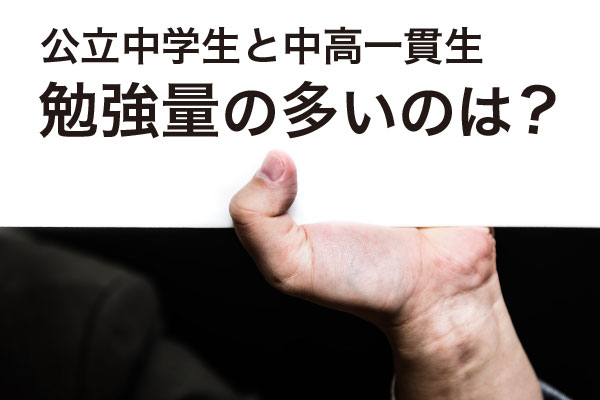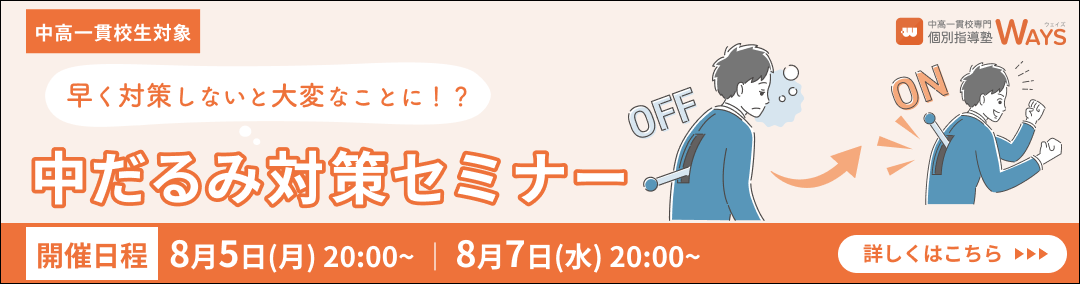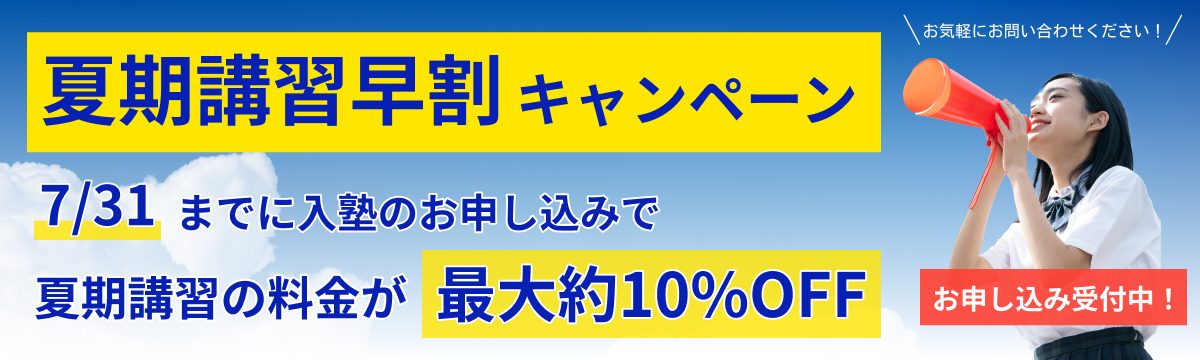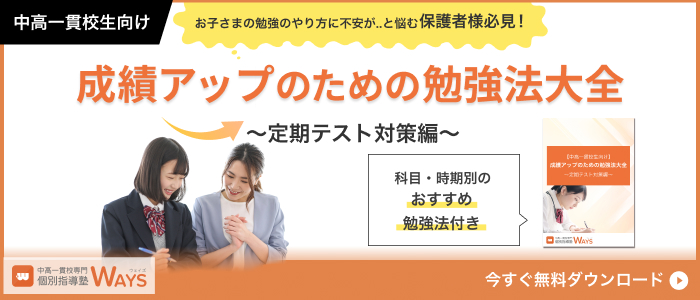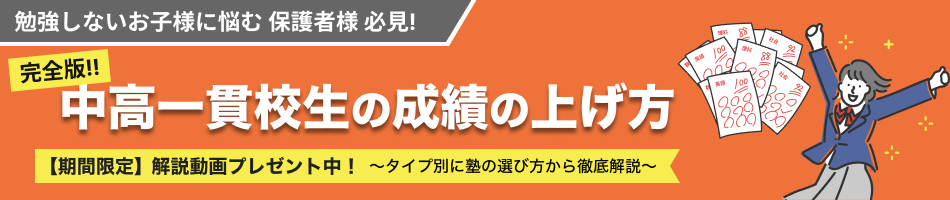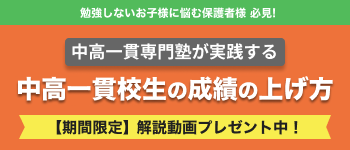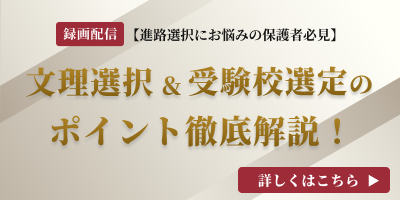受験勉強を朝にするメリットとは?進め方や習慣化するコツをご紹介


「受験勉強は朝がよいと聞いたけれど、何から手をつければよいかわからない」
「朝はうまく頭が回らない気がする」
このように、疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
早起きして勉強するのは一見すると大変そうですが、慣れれば簡単です。
今回は、受験勉強を朝にするメリットや、おすすめの勉強方法などをわかりやすく解説します。
続けるためのコツ・夜に勉強することとの違いもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
朝に受験勉強をしたほうがよいメリット
メリットがわからないと、早起きして勉強しようという気持ちにはなりにくいものです。
朝の受験勉強には、勉強のしやすさや、受験本番の練習など大きなメリットがあります。
早起きのモチベーションにするためにも、チェックしておきましょう。
受験勉強に集中しやすい
朝に勉強する1番のメリットは、集中しやすいことです。
朝は、1日を通してもっとも頭が回転しやすい時間帯といわれています。
とくに、朝起きてから3時間は「脳のゴールデンタイム」とされ、頭を使う勉強などに向いている時間。
なぜなら、朝起きたら頭の中の情報整理が終わっていて、クリアな状態であるです。
本来人は、眠っている間にその日に得た情報を整理しています。
脳に溜まっているさまざまな情報が、睡眠中に必要なものと不必要なものに振り分けられるのです。
さらに、眠ることで心身の疲れが回復します。
睡眠後の頭はまっさらにリフレッシュした状態。
余分な情報がなく勉強に集中できるため、考える力もアップしやすいとされています。
受験当日の練習になる
基本的に、受験当日は朝から試験がある場合が多い傾向です。
そのため、試験本番は朝早くから頭をフル回転させることが求められます。
朝の受験勉強は、本番同様の試験形式で全力を尽くす練習になるのもメリット。
普段から早起きをして勉強する癖をつけておけば、朝から問題を解くことに脳が慣れてくるでしょう。
受験当日と同じ条件で勉強すれば、本番のパフォーマンスが向上しやすいはず。
また、早起きする癖をつけておけば、試験中に眠くなる事態も防げます。
朝におすすめの受験勉強の進め方
朝の勉強方法がわからないままだと手探り状態で始めることになり、効率よく勉強できない場合も少なくありません。
そこで、朝に受験勉強する際、おすすめの進め方をご紹介します。
まずは朝食を食べる
まずは朝食を食べて、脳を起こしましょう。
集中して朝の受験勉強に取り組むためには、脳を正しい方法で覚醒させることが大切です。
朝食を抜いて勉強の時間に当てる方もいますが、その日のパフォーマンスが1日中悪くなる場合も。
農林水産省によると、脳はブドウ糖を使って活動するため、朝食を抜くと本来の活動ができません。
脳の活動に必要なエネルギー源が不足するため、パフォーマンスも悪化しやすくなります。
朝食には、ご飯やパンなど、糖質が多く含まれている主食がおすすめです。
また、朝食の前にはカーテンを開けるなどして、日光を浴びるのも脳を目覚めさせる効果があります。
勉強は復習から
気合を入れていきなり難しい問題を解こうとしたり、新たな知識を覚えようとしたりしても、起きてすぐは頭がうまく回りません。
そのため、まずは軽い復習から始めてみましょう。
頭が冴えてきてから難しい問題に取り組むと、効率よく勉強できます。
なお、朝は集中しやすく頭もリフレッシュしているため、考える力を必要とする科目に向いています。
理系科目をはじめとする記述問題や計算問題などは、朝の受験勉強にぴったりです。
朝の受験勉強を習慣化するコツ
朝の受験勉強は、継続することが大切です。
ここでは、習慣化するポイントをご紹介します。
起きる時間は徐々に早める
起床時間は、徐々に早めるのがコツのひとつです。
起きてから3時間は、勉強するのにぴったりな時間帯といわれています。
しかし、実際に起きてから3時間を確保するためには、かなり早い時間に起きなければいけません。
たとえば、8時半に家を出る場合、最低でも5時に起きる必要があります。
今まで7時半など、あまり早起きしてこなかった方が、いきなり5時台に起床するのは大変です。
早く起きることが負担となり、モチベーションの低下につながる可能性もあります。
そこで、いきなり早起きを目指すのではなく、30分ずつでもいいので少しずつ起床時間を早めてみましょう。
寝る直前のスマホは控える
寝る直前までスマホやパソコンを触るのは控えましょう。
スマホなどから放たれるブルーライトを浴びると目が覚めてしまい、睡眠の質を下げる原因のひとつといわれています。
睡眠時間が短いと、記憶力が低下します。
また体内時計が狂うため、心身の不調にもつながりかねません。
さらに睡眠不足では完全に疲れがとれないため、朝に勉強しても集中力が続かないのです。
量より質であると考え方を変える
受験勉強でやってしまいがちなのが、とにかく量をこなす勉強方法。
しかし、大切なのは量より質です。
とくに、受験生は受験勉強以外に、学校もあります。
そのため、平日の朝に勉強できるのは、学校に行くまでの間だけでしょう。
時間制限がある状態なので、量を求めると質の高い勉強ができません。
前日の夜に、翌朝どのような内容を勉強するか決めておきましょう。
あらかじめ勉強内容を決めておけば、限られた時間でも質の高い勉強ができます。
夜型勉強と朝型勉強の違い
夜の勉強と朝の勉強の違いは、勉強する内容です。
夜に勉強するなら、英語や古文など暗記系科目がおすすめです。
夜は記憶しやすい時間帯といわれています。
睡眠中、人間の脳はその日に得た情報を整理しています。
就寝直前の情報は整理されやすいため、より記憶に残りやすくなるのです。
夜の勉強の注意点は、時間制限がないため夜遅くまで勉強してしまうこと。
予防策として、時間を決める、翌日勉強する内容と区別しておくなどが挙げられます。
質の高い睡眠は、翌日の集中力アップなどパフォーマンスを高めてくれるでしょう。
朝は、単語などの記憶系よりも、文章問題など考察する問題が向いています。
朝と夜でそれぞれに合った科目を勉強すれば、効率よく受験勉強できます。
関連記事
勉強の効率を高めたい!効率アップのための方法を詳しく解説
まとめ
朝の受験勉強は集中力が高まり、受験当日のシチュエーションに沿って勉強できるのがメリット。
考察が多い理系や文章問題などが向いています。
効率よく勉強することで、受験に向けて着実に実力を伸ばしていけるでしょう。
しかし学生だけでは、本人にとって効率よい勉強内容がわからない場合も少なくありません。
また、中高一貫校生の場合は、受験モードに切り替えるのが難しく、勉強時間の確保自体がうまくできないことも。
そんなときは、「中高一貫校専門個別指導塾WAYS」の「大学受験対策」がおすすめです。
定期的な学習コーチングや長時間の個別指導で、中高一貫校生の考え方を受験モードに切り替えます。
たとえば、1日1時間以下の勉強量で中だるみしてしまった学生も、勉強する習慣が身につき、勉強時間を5倍確保できるように。
無料相談や無料の資料請求もできるので、気になる方はぜひお申し込みください。
投稿者プロフィール
-
中高一貫校生の定期テスト対策から大学受験・内部進学までをトータルサポートする個別指導塾。
中高一貫校用教材に対応することで各中高一貫校の定期テストの点数に直結した指導を行います。
低料金で長時間指導が受けられるため、家で勉強できない中高一貫校生でも塾の指導時間内で成績を上げることが可能です。
英語、数学をメインに指導を行っています。
最新の投稿