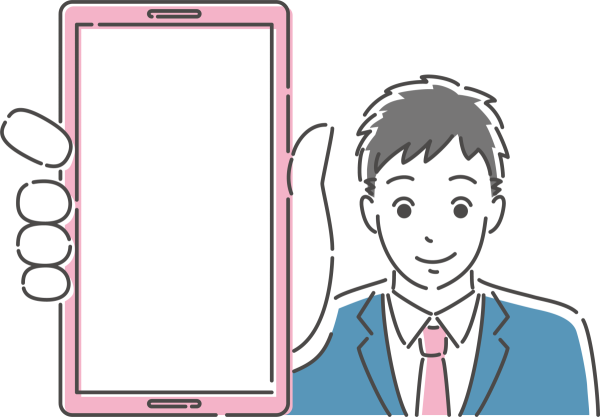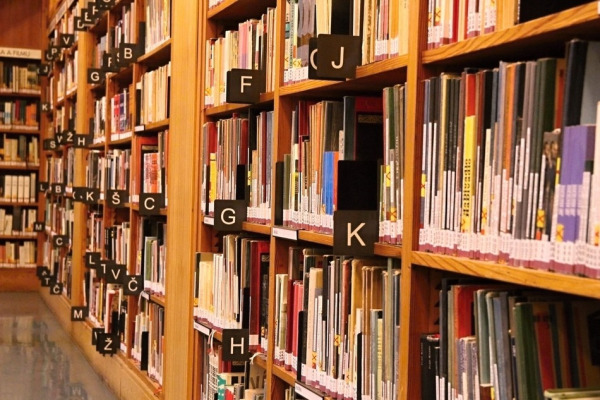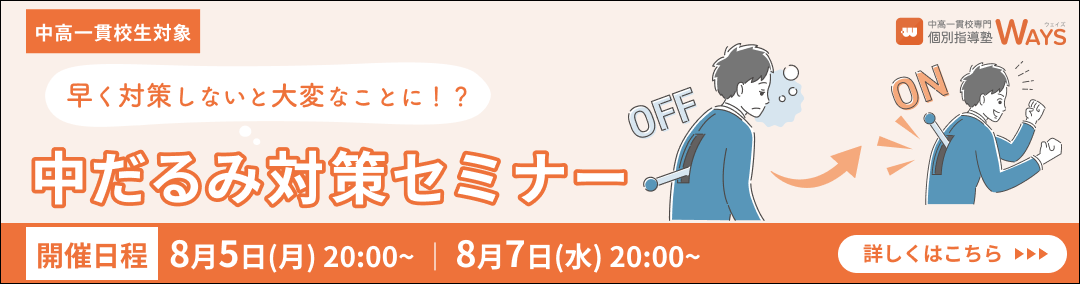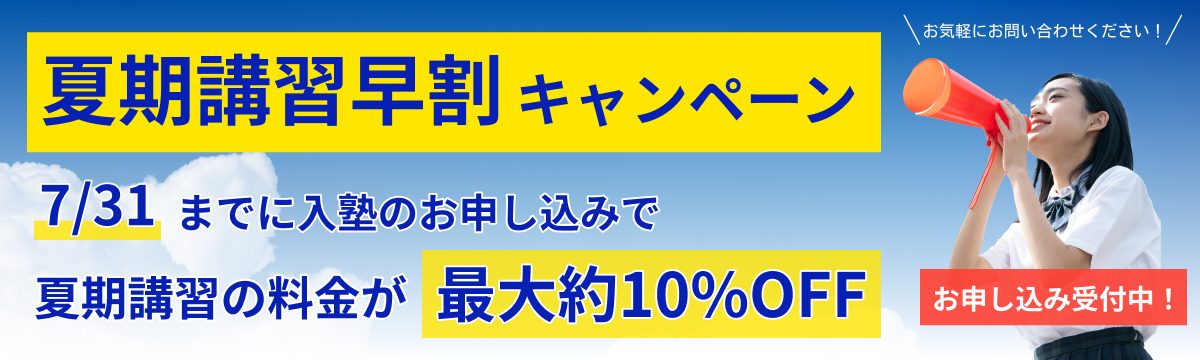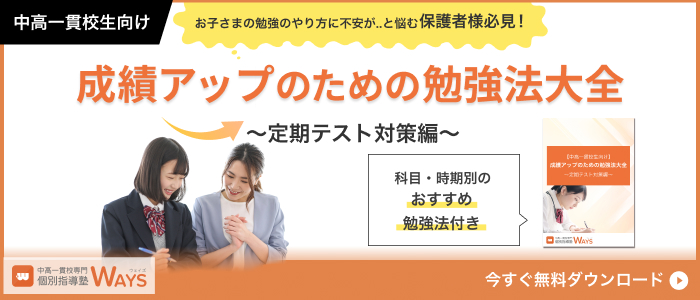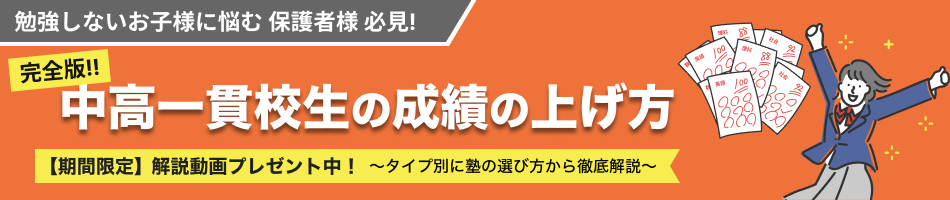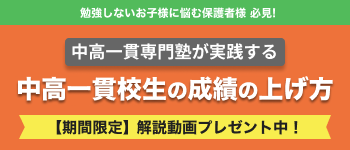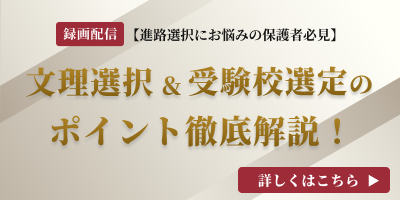【大学受験対策】小論文の書き方を解説!基本的な書き方やコツは?


「小論文の書き方が分からない」
「大学試験の小論文対策は何からしたらよい?」
と悩んでおられませんか?
今まで小論文を書く機会がなかったため、大学試験で必要になり焦る人も少なくありません。
本記事では小論文の書き方・勉強方法・押さえておくポイントなどをご紹介します。
小論文の書き方が分からずに悩んでいる方や、大学入試対策が必要な方は、ぜひ最後までお読みください。
このページの目次
小論文を上手に書く5つのポイント
小論文の書き方が全く分からないため、不安を抱えている高校生は少なくありません。
「そもそも小論文ってなに?」と思っている人もいます。
小論文の基本の書き方を覚え、コツを掴んで苦手意識を少なくしましょう。
本項目では、制限時間内に小論文を書く5つのポイントについて解説します。
小論文と作文の違いを理解する
小論文と作文の違いを、理解しましょう。
小論文は、課題に沿って自分の意見を論理的に述べるものです。
文章力はもちろんですが、理解力・識別力が欠かせません。
反対に作文は、読書感想文のように自分の感想や気持ちを自由に書くものです。
読書感想文のような文章は作文、論理的に言葉を組み立てる文章が小論文です。
3部構成を抑える
小論文を書く際は、序論・本論・結論の3部構成を抑えましょう。
| 3部構成 | 押さえるとよいポイント |
|---|---|
| 序論 | ・序論は小論文の方向性を決める大切な部分 ・序論は2〜3行で書く ・序論に自分の意見・結論を書いてよい |
| 本論 | ・序論で述べた意見や結論の裏付けになる情報を述べる |
| 結論 | ・再度意見を提示し文章をまとめる |
とくに、「序論」「結論」では、結論から書くことを意識しましょう。
結論から書きだすことによって、意見をしっかりと伝えられ、論理的で文章全体がまとまったものになるからです。
見出しを書き出す
文章を書き始める前に、全体の構成を考えましょう。
具体的には見出しを書き出して、内容をメモすることがポイントです。
簡単にメモすることで、ダラダラとした文章を書くことを防ぎ、内容がまとまりやすくなります。
小論文の文章のルールをおさえる
小論文の文章のルールをおさえた書き方をすることも大切です。
ルールの一例を、下記にまとめました。
- 一文(ワンセンテンス)が長くなりすぎない
- 文章の書き出しは1文字下げる
- 文章を統一する
文章は「だ・である調」を使うのが一般的です。
時間配分を考える
時間配分を考えた書き方を、意識しましょう。
時間内に記事を書くのに理想的な時間配分を、下記にまとめました(800文字・60分の場合)。
| 内容 | 時間配分 | 配分 |
|---|---|---|
| 分析 | 5~10分 | 形式ごとに設定されている課題文を読んだり、図や表を分析したりする |
| 構成を考える | 15~20分 | ・見出しを書く ・小論文の構成を組み立てる |
| 小論文を書く | 20〜30分 | ・本文を書く |
| 見直し | 5~10分 | ・誤字脱字のチェック |
きちんと時間配分をすることで、「時間が足りない」といった焦りを防ぎましょう。
大学受験を意識した小論文の勉強方法
小論文は、一般科目と違い勉強方法が分かりづらいので「いつから何を勉強したらよいか分からない」と、悩む高校生も少なくありません。
とくに、文章を書くのが苦手だと「大丈夫だろうか?」と、不安になるのではないでしょうか?
本項目では、大学受験を意識した小論文の勉強法について分かりやすく解説します。
小論文対策は3年生の春から本格的に行う
小論文対策は、志望校の入試で必要だと分かった段階から始めるのが理想です。
具体的には、1・2年生の時期に新聞やニュースをチェックして幅広い情報収集をすることを意識し、3年生の春から本格的に小論文の対策を始めましょう。
「ギリギリでもいいのでは……」と、思われるかもしれません。
しかし、文章力を短期間で身につけるのは難しく、時間が必要です。
文章力には個人差があるため、とくに苦手な人はできるだけ早く取りかかりましょう。
例文を真似して書いてみる
小論文の書き方が分からない場合は、参考書に載せられている例文を真似して書くとよいでしょう。
例文を真似して書くことで、小論文と作文の違いを理解することができます。
まずは、理想的な文章に触れることを、意識してください。
慣れてきたら、実際に小論文を書き始めましょう。
学校や塾の先生に添削してもらう
小論文の書き方をマスターするためには、書いた文章を学校や塾の先生に添削してもらいましょう。
自分で文章を書いただけだと、内容が偏ったものになり間違いにも気づけません。
アドバイスしてもらうことで、自分の癖を理解でき、よりよい小論文を書けるようになるのです。
小論文の3つの形式の違いを理解する
小論文には、テーマ型・課題文型・データ分析型の3つの形式があり、次の通りです。
| 形式 | 内容の説明 |
|---|---|
| テーマ型 | ・「〜について述べよ」とテーマが提示されるパターン ・与えられたテーマのうちから自分が伝えたい内容を選び意見を述べる |
| 課題文型 | ・「次の文章を読み意見を述べよ」と出題されるパターン ・文章の内容を理解する読解力と、小論文を書く文章力が必要になる ・大学入試で最も多い出題形式 |
| データ分析型 | ・図・グラフ・写真などの資料が提示され「資料を読み取り意見を述べよ」となるパターン ・図の解説ではなく、図から読み取れることをもとに意見を述べる必要がある |
3つの形式の違いを理解し、意識した記事の書き方ができるようになりましょう。
志望校の形式が分かっているのであれば、絞って勉強できますし、分からない場合は、どの形式にも対応できるよう満遍なく練習しておくことをおすすめします。
大学受験に合格するための小論文を書くコツ
大学入試対策のための小論文の書き方には、いくつかのコツがあります。
コツを押さえることで、よりよい小論文を書けるようになるでしょう。
下記では、大学受験に合格するための小論文を書く3つのコツについて解説します。
ていねいな文字で書く
文章の内容だけでなく、ていねいな文字で文章を書くことも、意識してください。
文字がていねいだと、読む人の印象がよくなりますし、相手に敬意を払うことにもなるからです。
また、ていねいな文字でないと、採点の際、誤読されるおそれがあります。
誤読のせいで文章の意味が変わってしまうと、文意が伝わらず、減点につながることもあるでしょう。
課題の意図を理解する
課題の意図を理解し、テーマに沿った文章を書くことを忘れてはいけません。
小論文を書く以前に、課題の意味を間違わないことが先決です。
課題の意図を正しく理解する判断力を養うためにも、学校や塾の先生に添削を頼みましょう。
自分の意見をしっかりと伝える
自分の意見をしっかりと述べることも、大切です。
とくに、データ型の小論文の場合、出されたデータの解説を述べただけの文章にならないように注意してください。
データから読み取った情報を基に、自分の意見を含めた文章を書く必要があります。
まとめ
小論文の勉強の際には、見出しを書きながら構成を考え、3部構成や時間配分を意識して文章を書きましょう。
先生に添削してもらい、アドバイスをもらうことも大切です。
「文章を書くことが苦手だから」と、焦る必要はありません。
一つひとつポイントを押さえながら勉強することで、小論文の書き方をマスターできるでしょう。
ほかの科目の勉強法については、以下の記事で紹介しています。
あわせて参照してみてください。
大学受験で得点源になる!国語(現代文・古文・漢文)の勉強法
大学受験英語では順番が一番大事⁉おすすめの順番と具体的な方法を紹介
投稿者プロフィール
-
中高一貫校生の定期テスト対策から大学受験・内部進学までをトータルサポートする個別指導塾。
中高一貫校用教材に対応することで各中高一貫校の定期テストの点数に直結した指導を行います。
低料金で長時間指導が受けられるため、家で勉強できない中高一貫校生でも塾の指導時間内で成績を上げることが可能です。
英語、数学をメインに指導を行っています。
最新の投稿