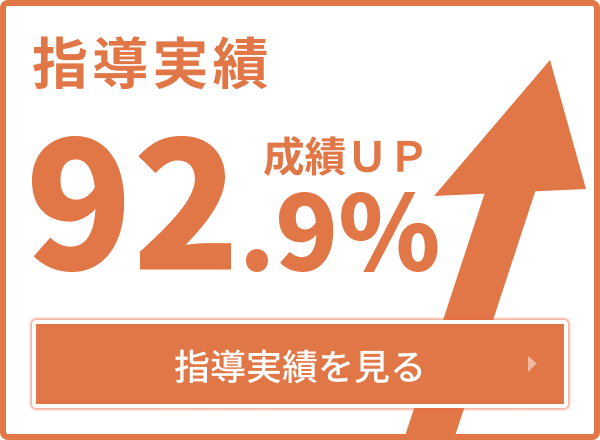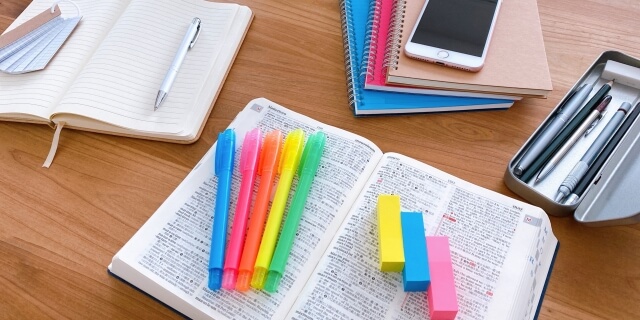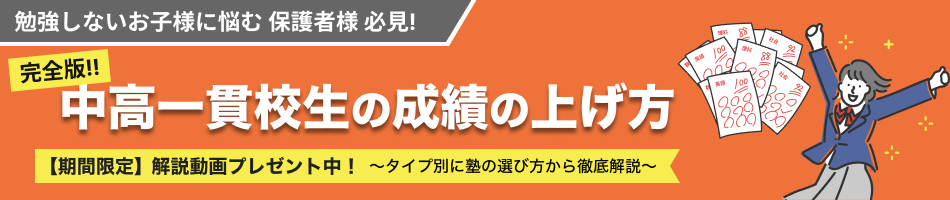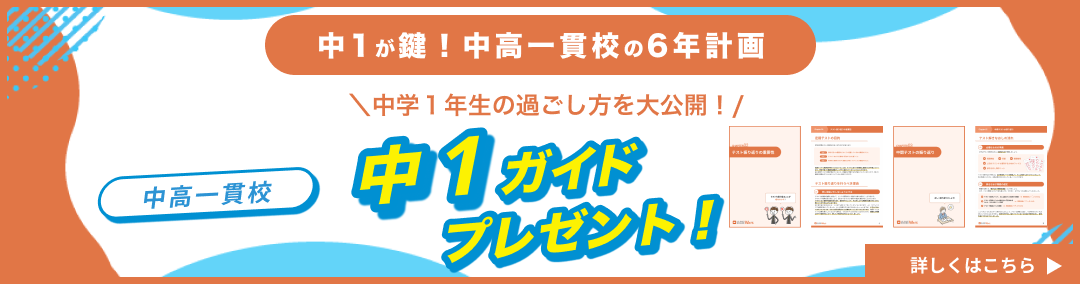大学受験生に必要な睡眠時間は?良質な睡眠をとる方法をご紹介


「本当は早起きして勉強したいけれど、朝なかなか起きられない」
「休日はお昼近くまで寝てしまう」
このような人はいませんか?
どんなに大学受験の勉強が忙しくても、睡眠時間の確保は必須です。
十分な睡眠をとらなければ、勉強効率も下がるため、学力向上につながりにくくなってしまいます。
本記事では、受験生に必要な睡眠時間と十分な睡眠時間をとることで得られる効果、良質な睡眠をとる方法をご紹介します。
睡眠をうまく活用して、勉強効率もアップさせましょう!
このページの目次
大学受験生に必要な睡眠時間は何時間?
授業中や勉強中に眠くなってしまう人は、睡眠時間が足りないもしくは良質な睡眠がとれていない可能性があります。
では、大学受験勉強中の高校3年生に必要な睡眠時間は、何時間くらいでしょうか?
国立睡眠財団は、思春期の睡眠時間は8~10時間を推奨しています。
しかし8時間睡眠をとるのは、なかなか難しい受験生が大半ではないでしょうか?
睡眠は、レム睡眠とノンレム睡眠が約1時間半のセットになって繰り返されています。
4セットで6時間、5セットで7時間半です。
しかし6時間では睡眠時間が短すぎ、長期間続けると脳のパフォーマンスが落ちるといわれています。
そのため、7時間半くらいの睡眠がとれるのが理想といえそうです。
睡眠時間の確保は大学受験に効果的
睡眠時間が十分でないと、体内リズムが崩れ「夜眠れない」「たくさん寝ても寝足りない」など、身体に悪影響を及ぼします。
一方、上質で十分な睡眠は、眠るだけで大学受験に役立つ効果が期待できます。
しっかり寝た方がよいと実感できる、4つの効果を確認してみましょう。
疲労回復が期待できる
多くの人が知っている睡眠の効果が、疲労回復です。
睡眠中に分泌される成長ホルモンは、筋肉の成長を促したり、壊れた内臓の細胞を再生したりするなど、身体の機能を良好に保つ働きがあります。
勉強が原因の目や肩の痛みや全身の疲労感は、良質な睡眠をとることで解決できます。
もしも一晩寝ても疲れがとれない場合は、良質な睡眠がとれていない、もしくは疲れすぎの可能性があるでしょう。
免疫機能が保たれる
睡眠中に分泌される成長ホルモンは、免疫機能にも大きな影響を与えます。
成長ホルモンは、免疫力を強化する役割を担っています。
体調を崩してしまうと受験勉強にも影響を与えてしまうため、免疫力は高めておきたいものです。
睡眠の力を借りて、身体を丈夫にしましょう。
覚えたことを定着させられる
睡眠中に脳内では、その日にあった出来事や覚えたことなどの記憶の整理と、記憶の定着を行っています。
つまり、その日覚得た内容を長期記憶として定着するのを睡眠が助けてくれます。
しっかり眠ることで、知識が定着するなら楽でよいですよね。
とくに暗記は、寝る前と起きてすぐに行うのが効果的です。
寝る前30分だけ暗記する
寝ている間に勉強内容をしっかり定着させるためにも、英単語や歴史上の人物など、暗記したいものは寝る前に行うのがおすすめです。
寝る30分ほど前から集中的に暗記しましょう。
知識を定着しやすくするポイントは、暗記をした後スマホを見たりゲームをしたり余計なことはせず、すぐに眠ることです。
これにより、無駄な情報が脳内に入ってくるのを防ぎ、より記憶にとどめやすくなります。
起きてすぐ復習をする
次の日起きてすぐに、前日に覚えた内容を復習しましょう。
脳は、何度も同じ情報が入ってくると「これは重要な情報だ」と認知し、長期記憶にとどめようとします。
夜暗記するだけでなく、朝と夜セットで行うことで、より暗記力を高められるでしょう。
また、朝目覚めてからの3時間は、脳のゴールデンタイムとも呼ばれています。
リセットされた脳が活発に動き始める時間で効率よく勉強が進むため、少し早起きして、暗記以外の勉強をするのもおすすめです。
精神が安定する
十分な睡眠は、精神的にもよい効果があり、ストレスや不安感を減少させ、精神を安定させます。
大学受験の期間は、勉強面で何かとストレスを感じやすいものです。
誰かに話を聞いてもらったり、気分転換をしたりすることでもストレス発散できますが、あわせて意識的に睡眠時間の確保ができるとよいですね。
大学受験のために良質で適度な睡眠時間をとる方法
大学受験のためにも、良質な睡眠は重要です。
よい睡眠は、昼間の過ごし方で変わります。
ちょっとした心がけで高い効果が期待できるため、次にご紹介する4つのことをぜひ意識してください。
身体を動かす
軽いランニングや早歩きでの散歩など、身体を動かすことで寝つきがよくなります。
寝る3時間ぐらい前に体を動かすと、上昇した脳の温度が下がる頃に入眠できるため、スムーズに眠りにつけるでしょう。
ただし寝る直前に激しい運動をすると、身体が興奮してしまい逆効果になるため注意してください。
朝日を浴びる
起きたらすぐに朝日を浴びる習慣をつけましょう。
体内時計がリセットされ、スッキリ起きられるようになるだけでなく、良質な睡眠もとれるようになります。
朝食をしっかりとる
乳製品や豆類、バナナなどタンパク質を朝食にとると、昼間はセロトニン、夜間メラトニンの分泌を促進します。
セロトニンは、精神を安定させストレスを和らげてくれます。
またメラトニンは睡眠ホルモンともいわれ、自然な眠りを促す物質です。
昼夜問わず、大学受験に高い効果が期待できるため、朝食はしっかり食べましょう。
夜間はスマホやタブレットを控える
夜間のスマホやタブレットを使用すると、強い光を浴びることにより脳が昼間だと勘違いしてしまいます。
その結果メラトニンの分泌が抑えられてしまい、深い眠りを妨げます。
よい眠りをとるためにも、とくに寝る前に間近で光を浴びないようにしましょう。
スマホやタブレットをベッドの近くに置くと、つい手を伸ばしてしまうため、少し離したところに置いておくのがおすすめです。
まとめ
大学受験を控えた高校生の理想的な睡眠時間は7時間半ほどです。
良質で適切な睡眠時間を確保することで、日中のパフォーマンスの向上や精神的な安定も得られます。
大学受験にとってはよいことずくめです。
無理に遅くまで勉強するのではなく、決まった時間に寝起きし、睡眠のサイクルをつくりましょう。
また、遅い時間に眠気と戦いながらダラダラ勉強するよりも、早朝に短い時間でも勉強した方が、密度の濃い勉強ができます。
受験勉強が大変で焦る気持ちもあるかもしれませんが、睡眠の大切さを知り、しっかり身体を休めたうえで勉強しましょう。
投稿者プロフィール
-
中高一貫校生の定期テスト対策から大学受験・内部進学までをトータルサポートする個別指導塾。
中高一貫校用教材に対応することで各中高一貫校の定期テストの点数に直結した指導を行います。
低料金で長時間指導が受けられるため、家で勉強できない中高一貫校生でも塾の指導時間内で成績を上げることが可能です。
英語、数学をメインに指導を行っています。
最新の投稿
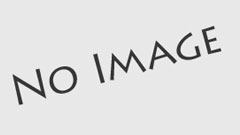 一貫教育コンパス2024年10月23日専門家に聞いた!ネットトラブルを事前に防ぐ お悩み相談会
一貫教育コンパス2024年10月23日専門家に聞いた!ネットトラブルを事前に防ぐ お悩み相談会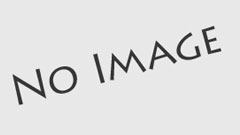 一貫教育コンパス2024年10月23日親子で知ろう!先輩大学生のリアルな生活を大公開
一貫教育コンパス2024年10月23日親子で知ろう!先輩大学生のリアルな生活を大公開