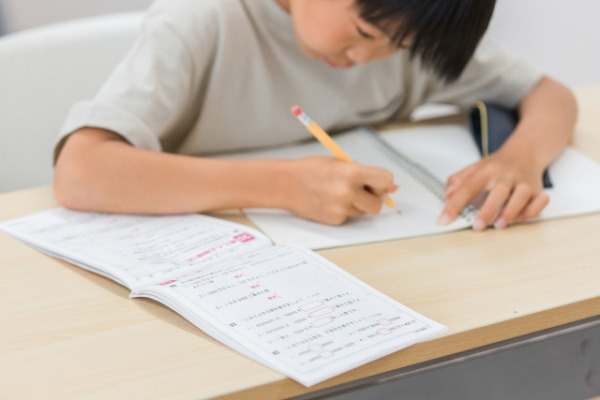中学受験で、真面目にコツコツ取り組むタイプの子の場合、頑張っているのに偏差値が上がらないケースが少なくありません。
もともと中学受験では偏差値が上がりにくいため、志望校合格レベルに届いているのであれば、心配しすぎず、お子さまの努力を認めるアプローチが合格への近道です。
どうしても不安な方のために、
・やるべき勉強ができているかのチェックリスト
・中学受験の終盤に合格を勝ち取るための学習法
も、あわせて解説します。
このページの目次
中学受験は偏差値が上がりにくいとても厳しい受験
中学受験は限られた子だけが取り組む受験です。受験生の多くが、学校では優秀な成績を修めており、そのなかで成績を上げるのは簡単なことではありません。
まずは、データをもとに私立中学に通う子の割合と、筆者が娘の受験で実際に感じた割合についてお伝えします。
私立中学に通う子は1割にも満たない
文部科学省の「令和6年度学校基本調査」によると、2024年度の私立中学校に通う子どもの割合は全国で約7.9%と、あまり多くありません。
ただし都道府県ごとの差は大きく、全国トップの東京都では26.3%と、小学校受験や中学校受験が盛んな様子がうかがえます。
一方で、東京都に隣接している千葉県は、6.9%と低めの数値です。
教育熱心な家庭や向上心の高い子どもが集まるため、非常にハイレベル
中学受験は、同じ都道府県の中でも、在住エリアによって受験の割合に違いがみられるのも特徴です。
例えば、筆者が住む京都の例をみてみましょう。
京都市内では受験者がクラスに数名いる学校が多く、中学受験が比較的盛んなエリアといえます。2024年度の私立中学に通う子どもの割合をみても全国3位、14.1%です。
一方、京都市外だとそれほど中学受験が盛んな印象はありません。筆者の周りではクラスに1人いるかどうか、学年に10人も満たないほどでした。
京都のなかでも受験者は都心部に集中しており、地域差の出やすい受験という印象を受けます。
しかも、受験をする子は学校で優秀といわれる子ばかり。学年トップと注目されていた子でも、受験では苦戦を強いられ、残念な結果を迎えていました。
このように、中学受験には一部の教育熱心な家庭や、向上心の高い子どもが集まるため、非常にハイレベルな環境です。偏差値が上がりにくいのは必然といえるでしょう。
学校のカラーテストは満点でも、塾では偏差値30台
筆者の娘も中学受験をするまでは、学校の勉強に困ったことはありませんでした。
公立小学校のカラーテストはほとんど満点。やや不得意な分野でも80〜90点をたまに取る程度と、成績はいつも褒められていました。
幼少期から公文に通っており、2〜3学年上の問題を解いていたため、勉強の基礎があったから困ることがなかったのだと思います。
しかし、そんな娘も中学受験を始めると、一気に雲行きが怪しくなります。
入塾当初の模試では、偏差値30台と無残な結果に。模試は毎月行われ、塾の校舎内で最下位レベルになったこともありました。
「塾での平均レベル=世の中の優秀レベル」を親がしっかり自覚する
中学受験を始めると周囲の学力レベルが一変します。
塾内での子どもの立ち位置が気になったり、なかなか上がらない成績に歯痒さを感じたりすることも多いでしょう。
しかし、一般的な小学生のトップクラスたちが集まる環境のなかで、偏差値50前後の平均レベルまで達しているのであれば、十分に健闘している立ち位置といえます。
塾内で平均的なポジションであっても、世の中では優秀なポジションに属することを、親がしっかりと自覚することが大切です。
子どもの現状を客観的に受け止めるように習慣づけることで、親は心穏やかに過ごしやすくなるでしょう。
偏差値の停滞は努力を継続している証拠。認めてあげることが合格への近道
偏差値があまり変わらない状態が続くと、停滞していると感じる親御さんは少なくありません。停滞と思われやすい状態への認識を見直し、本来の状況を正しく理解しましょう。
偏差値キープは停滞でなく維持。見方を変えて努力を認めることが大切
模試の成績表が返ってくるたび、親はつい成績アップを期待してしまうもの。しかし、厳しい環境では成績を上げるどころか、維持することも決して簡単ではありません。
お子さまが成績を維持しているときは、周りに負けないように努力を継続できている状態です。
優秀な子たちが必死に努力を重ねる状況で、毎回同程度の成績を維持できているのであれば、十分に頑張っているといえます。
成績について「停滞」でなく「維持」できているという認識に改めることで、お子さまの努力を快く認めてあげやすくなるでしょう。
努力を認められた子どもは、勉強の意欲が高まりやすくなる
偏差値が上がらず停滞していると感じていたときは、「なかなか上がらないね」「勉強量を増やしたほうがいいと思う」と、努力不足を指摘するような声かけが多かったように思います。
模試の返却のたびにこのような言葉をかけられると、成績表を親に見せることに抵抗を感じるのでしょう。当時の娘は、私からの評価に怯えているような印象を受けました。
しかし、停滞でなく維持できているという認識に改めてからは、私の声かけも変わりました。
成績表を見たときに「今回も頑張ったね」「この分野は苦手だったのに落とさずできたね」と、努力を認める言葉をかけることで、積極的に成績表を見せてくるようになったのです。
「〇〇ができるようになってすごいね」「ここは惜しかったから次は確実に取りたいね」
と細部まで見ることで、娘からも
「〇〇を頑張ったの!」「次はここも取れるようにしたい」
と前向きな言葉が返ってくるように。会話がポジティブな内容になるにつれて、勉強の意欲も高まっていきました。
急成長する子に抜かれても慌てないで。コツコツタイプの強みは粘り強さ
受験終盤になると、塾内でのポジションに変化が出ることもあります。
筆者の周りでもよく聞いたのが、やる気を出した子が急成長するケースです。
成績が低迷していたはずの子が、やる気を出した途端にめきめきと成長し、コツコツ取り組んでいた子が一気に抜かれてしまうのです。
受験終盤で抜かれてしまった子どもは動揺しやすいですが、本人の学力が志望校のレベルに届いているのであれば問題ありません。
不安になっている場合は、気にする必要がないことを伝え、安心させたうえで、これまでどおり継続できるように応援してあげましょう。
コツコツタイプの強みは、粘り強い継続と安定性
コツコツタイプの子は成績面での大きな跳躍は起こりにくいものの、成績を維持できる安定性の高さが魅力です。
粘り強い継続は、中学受験において大きな武器。苦手な分野を克服したいときも、持ち前の粘り強さであきらめずに取り組むことができます。
得意分野は確実に点数を取れるように、苦手分野は失点を防げるように、粘り強さを活かして安定性を高めていけるため、着実な成長が期待できるでしょう。
どうしても心配な親のための、やるべき勉強チェックリスト
コツコツタイプの特長や強みがわかっても、やはり心配が尽きないという方もいるでしょう。次の6つがしっかりできているかどうかを確認してみてください。
これができてたら大丈夫!やるべき勉強チェックリスト
中学受験で確実におさえておきたい勉強について、チェックリストにまとめました。
以下のポイントをおさえておけば、多くの大学附属校や平均レベルの学校に合格水準に届きやすくなるはずです。
- 塾の宿題をサボらずにきちんとこなす
- 小テストや模試で間違えた問題を放置せず解き直す
- 分からない問題に時間をかけず、先生に質問する
- 算数の計算問題でほぼ全問正解できるように毎日解く
- 国語の漢字や語彙でほぼ全問正解できるように毎日解く
- 基本問題で8割程度取れるように演習量を増やす
算数・国語がほぼ全問正解できていない場合は、ドリル等を毎日の習慣に
計算や漢字・語彙の問題などをほぼ全問正解できない場合は、ドリルなどを用いて毎日の習慣にすることをおすすめします。
筆者の娘の場合は算数が苦手だったので、毎日20分程度していた朝勉強を、計算の時間にあてました。
一方、得意科目の国語は、宿題として漢字と語彙がいつも大量に出されていたため、宿題をするだけで問題なく好成績を維持できていたと思います。
計算や漢字・語彙の演習は、塾でドリルを使用している場合はそれを使うとよいでしょう。
筆者の娘が塾で使用していた問題集は、計算問題を毎日解けるように設計されていたので、習慣として続けることができました。
量が物足りないときは、以前に解いた問題をもう一度解いてみるなどして、問題に触れる量をできるだけ増やすとよいでしょう。
繰り返し解くためにも問題集には書き込まず、ノートを使用して解くことをおすすめします。
直接書き込みたい場合はテキストを原紙とし、コピーした用紙に書き込むと繰り返し使えます。
苦手分野は学習量を増やし、得意分野は必要量を継続したことで、次第にバランスよく点数を取れるようになっていきました。
基本問題で8割程度取れていない場合は、間違えた問題を繰り返し解く
基本問題での失点は受験校によって目安が異なります。大学附属校や偏差値50前後の平均レベルの学校であれば、基本問題は8割程度は取れるようにしておきたいところです。
8割に満たない場合は間違えた問題を繰り返し解き、分野を問わず対応できるように取り組むとよいでしょう。
基本問題の演習は、通っている塾の問題集から基本問題を抽出して行うのがおすすめです。
塾の問題集以外にも手を出したくなるかもしれません。
しかし、基本問題が定着していない状態で、さらに他の問題集に手を出しても、消化不良の問題が増えていきます。
使用している問題集を繰り返し解くことを重視しましょう。
偏差値が徐々に低下している場合は、基礎が固まっていない可能性大
周りの受験生たちが基礎を固めていくなかで、不得意な分野があると周りよりも失点が増えていき、偏差値が少しずつ低下しやすくなるでしょう。
偏差値が下がってきたら、不得意分野や定着できていない分野があるサインだと捉えてみてください。
偏差値の低下に落ち込むのではなく、失点の多い分野を洗い出して基礎をしっかりとやり直すことが大切です。
未定着の分野を洗い出すのが難しい場合は、模試の成績表にある設問別の成績表をチェックしてみてください。
一般的に、設問別の成績表では得点率がグラフ化されているため、どの分野で失点しているかを確認できます。
失点の多い分野の基本問題を塾のテキストから抽出し、自力で解けるようになるまで繰り返し解くとよいでしょう。
中学受験の終盤戦で、合格を勝ち取るために取り組むべき学習法を解説
多くの中学受験では、中学受験の終盤戦には偏差値が出なくなります。学力を相対的に判断しにくくなる時期ですが、この時期こそが大幅に伸びるチャンスです。
ここでは、合格を勝ち取るために取り組むべき学習法をご紹介します。
「頑張って当然」の世界。真面目にこなすだけでは差がつきにくい
コツコツタイプのお子さまにとって、与えられた課題を真面目に取り組むのは得意でしょう。
しかし、受験本番が迫る終盤戦は、これまで手を抜いていた子も熱心に取り組む時期です。
娘もコツコツ頑張っていたものの、終盤では偏差値がじわじわ降下しており、下がった状態のまま模試が終わりました。
一般的な水準で考えると多量の演習量をこなしていたとしても、中学受験では多くの子が同様以上の勉強量をこなします。
そのため、コツコツ取り組むだけでは周りと差をつけることが難しくなるでしょう。
徹底した解き直しによる基礎固めが合格への近道
計算や漢字、語彙、基礎などは一朝一夕で身につくものではなく、日々の積み重ねが不可欠です。
中学受験の大学付属校や平均レベルの学校を狙うなら、基礎をいかに安定して取れるかどうかが合否のカギを握ります。
基礎を安定させるには、苦手分野を自覚し、自力で解けるようにすることが重要です。苦手分野を洗い出したら、その分野の基礎問題を繰り返し解きましょう。
間違えた問題は確実に正解できるようになるまで、2周3周と解き直す習慣をつけることが大切です。
何度も解き直すことで基礎が定着していき、合格水準に近づけます。
しかし、ただ闇雲に繰り返し解いても、回答を書き写すようなやり方では成果が得られません。基礎を定着させるための4ステップを以下にまとめます。
基礎を定着させる「解き直し」具体的なやり方4ステップ
ステップ1:間違えた問題に✔️をつけて解き直す(1回目の解き直し)
ステップ2:再度間違えた問題に✔️をもう一つつけ、解説を読んで理解できるようにする(2回目の解き直し。解説を読んでも理解できない場合は講師に質問する)
ステップ3:✔️✔️の問題をもう一度解いてみる(3回目の解き直し)
ステップ4:数日後に✔️✔️の問題を解き、自力で解けるか確認する(4回目の解き直し)
上記の4ステップを解き直しのルールとして取り組むことで、しっかりと基礎が定着します。
ステップ1のポイント:解き直してみることで、間違えた原因を突き止める
間違えた問題に✔️をつけただけの状態では、また原因を把握できていません。解き直してみることで、間違えた原因を突き止められます。
ステップ1の時点でスムーズに正解できる場合は、ケアレスミスや計算ミスだと考えられるでしょう。
ステップ1で間違えてしまう場合は、本質を理解できていない可能性が高いため、✔️をもう一つつけて、自力で解けるようになるまでじっくりと向き合いましょう。
ステップ2のポイント:疑問点を残さない
解説を読んでも理解できなければ、塾の講師に質問して、疑問点を残さないことが大切です。
ステップ3のポイント:その日のうちに自力で解けることを確認
解説や質問を通して理解できたと感じても、自力で解けるかどうかを確認することが大切です。必ずその日のうちにもう一度解き直してみてください。
ステップ4のポイント:数日置いて、定着していることを再確認
さらに、数日置いてから✔️✔️の問題をもう一度解き直してみることで、本当に定着しているかどうかを確かめられます。
ステップ4を終えたあとでも、また間違えてしまった場合は✔️✔️✔️として、理解できるようになるまで粘り強く原因を分析し、解き直してください。
確実に解けるようになるまで、ステップを重ねていきましょう。間違えた回数分だけ✔️を増やしていくことで、お子さまが取り組むべき要注意問題としてピックアップしやすくなります。